昨日は、主に住宅ローン控除の税務相談を依頼され、幹部及びスタッフ7名でお伺いする。
住宅ローン控除は、年々、控除額が減少している。
控除額=年末ローン残高×控除率
年末ローン残高の最高限度額が一時期、5千万円であったものが、平成20年入居の場合、2千万円までとなる。
ほとんどの給与所得者にとって、確定申告は未知の領域。
住宅を購入して多額のローンを抱えた場合、確定申告を行えば、納税したお金が還ってくる。
「還付金の上限と勘違い」
いつも、こういう説明会では、実際の源泉徴収票を取り出して頂き、お客様が1年間納付した金額を見て頂く。
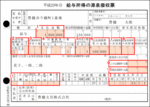
上記源泉徴収票例は、豊橋市から引用(サンクス!)
あの小さい紙の右上側に源泉徴収税額と書いてある。
「国からお金が戻ってくるということで勘違いされる方もおります。
国に納税した以上にお金は還ってきません。
その源泉徴収税額を上限にお金が還ってきます。」
金沢会計人 のすべての投稿
ストローズ新年会
昨日は、ストローズ新年会。
![]()
ストローズも会員数が16名に達し、うち12名が2009年度事業経営計画&戦略を熱く語る。
当初、一人15分プレゼンとしたところ、話し始めたらとても時間内に収まらない。
私も時間オーバーとなり、14時終了予定時刻も気付けば、15時30分!
会員の中から、タイムキーパーが必要とご意見を頂戴する。
そうしましょっ!
事業承継は、経営権と財産権の2つの完了をもって貫徹する。
経営権の承継につき、学習させて頂いた。
感謝です、ハイ。
この模様を収録すれば、参考になる後継者も多いだろうと思う。
ストローズ樋口会員も自身のブログでこの新年会を紹介頂いている。
いけいけ事務長かっちゃんのブログ
第15回「きんどん会」新年会
昨日の午前中は、MMPGの研修会。
午後から金沢へ移動して、TKC北陸会の賀詞交換会へ。
小松空港から高速バスで異動し、そのまま会場へ直行^^
さらに、中座して、異業種交流会「きんどん会」の第15回新年会へ。
恒例の会員挨拶は、トップバッター。
以下、60人が挨拶する。
全員がスピーチを終わるまで、約1時間40分かかった。
司会のMROの笹原常務取締役によれば、私の挨拶は「50秒」とのコメントを頂く。
事前に用意していた、新年会の挨拶(異業種交流会ヴァージョン)メモにこう書いてある。
「今年は、若手会員も増加したことからやや弛緩した挨拶としよう。
まずは、自己紹介。
こう見えて39歳となりました。(どよめきが起こると予想)
こう見えて税理士です。(そんなリアクションはないと予想)
30名ほどの会計事務所を母体としたコンサルティング会社で働いております。
お医者さんに特化している部門があります。
会員の皆様の中には、医療福祉のイメージが強く、ドクターしかお客様がいないと思っている方がいらっしゃるのではないかとご懸念しています。
今年、医業経営の学会で全国から800名ほどの会員が此処金沢へ集結します。
事務局を担うことから、新聞紙上でも、「木村」=医業のイメージがより大きくなるのではないかと。
決してそんなことはございません。
中堅オーナー企業、資産家を中心とした一般のお客様が、全体の半分以上を占めます。
さて、きんどん会員の中に、公認会計士や税理士の先輩先生もいらっしゃいます。
私どもにも、中堅企業向けの提案の際は、平等の機会を与えていただきたく、これはお願いでございます。
私自身、事業承継&組織再編を研究テーマとしております。
微力ながら何かお手伝いできればと思います。
医業を強調しつつ、他の会員の皆様へもアピール。」
うむむ。。。
事前に用意していた原稿は全部言えず、あまり「笑い」がなかったのは事実(苦笑)
来年は、よりくだけた感じでいこうと思う。
時系列で整理してみよう
昨日は朝からホテルで仕事。
今回は時系列でメモどうり追っていこう^^
1.7:30~10:00
出張中の申告書作業は初体験。
プリンターがなくても、PDFファイルでお客様に送付可能であり、遠隔地においても、メールさえあれば作業可能ということがわかる。
電卓がなかったので、ホテルから借り、小さい慣れない電卓で別表を作成してみる。
なんとか10時には終了する。
経理担当者が変わったばかりで不慣れということもあったのでしょう。
今回の不測の事態となった訳だが、今後のこともあり、今度きっちり指導させて頂こう。
2.11:00~13:00
急いで出かける用意をし、APAホテルを退出。
11時までにチェツクアウトせねばならぬ。
仕事するうえで大変、狭かったので、次回からホテル選択は再考することとする。
情報化認定の二次試験は、レポートの作成が義務づけられている。
その作業場所と選んだのは、スタバのようなカフェ。(名前はわからぬ)
コンセントのある場所を選択し、一心不乱にレポートの作業。
ここで、公表しても問題ないが、23日に二次試験後発隊が控えているので、やめておこう。
いずれにせよ、事務局へは提出し、受け取った旨の返信を頂く。
なんとか12時30分には終了し、続いて「税理」の原稿を校正する。
3.14:00~
MMPG全体会に参加するため、赤坂から御成門まで電車で移動。
行く先は、懐かしの職場から程近い東京プリンスホテル。
会議終了後は、4会計事務所の事例取り組みにつきご教授いただく。
A.
院長の希望は、診療所には事務長がいないので、会計事務所に事務長の役割を期待している。
B.
事例発表会を1年に1回継続している。
継続すれば、質が上がる。
何よりも学習を継続することが大事。(学習できる組織を目指す)
社員が学習できる機会、成長する場所を提供する。
なぜ、続いたか?
ポイントは強制とチェックはしないこと。
継続するには、決して批判することなく、褒めて励ます。
C.
経営者の思いを聞く。耳が2つ。口は一つ。
D.
お客様から依頼されたものはサービスではない。
減収時代のリスクマネジメントの新しい視点として、夢を語る計画ではなく、リスクを回避する事業計画を提供。
4.19:00~
賀詞交換会が始まるや否や、先生方とのご挨拶を開始。
社会医療法人を日本で2番目に設立した先生など豪腕の持ち主ばかり。
お客様のお役立ちを常に考えている勝ち組事務所の先生方との交流がこの会の基盤だと改めて実感。
最後に、大御所の先生から、二ノ宮尊徳の言葉を頂く。
「この秋は、雨か嵐か知らねども、今日も一日、田の草を刈る。」
(田植えをしてから、秋の刈り取りまでの、期間中に台風が来るかもしれない、どんな自然災害がくるだろうかと考えたら、眠れなくなるほど心配になることもあるが、それはそれとして、先ず今、出来ることをしっかりやる)
正月休みに数冊の本を読むに、視点や距離感により、100年に1度の大恐慌、千載一遇のチャンスなど両極端の見解が多い。
悩んでいる経営者も多いであろう。
拠り所は、公正無私の理念。
行動は、脚下照顧。
足下を見て、役割分担をし、それぞれ今日の務めを果たすことが大事。
農作も秋に台風が来るからといって、春に種まきしないことはない。
含蓄のある言葉を噛みしめたい。
情報化認定コンサルタント二次試験終了!
昨日、認定登録医業経営コンサルタント「情報化認定コンサルタント」の二次試験受講のため、東日本橋にある協会研修室へ向かう。
9時から17時30分まで3つのケーススタディを行った。
ABCD4つのグループに分かれ、討議する。
私はBに配属される。
5人のチーム中、職業会計人は二人。
医療現場にいないので、具体的な内容がイメージできない。
ただ、自分の役割は何処にあるのかを常に考えて、ケーススタディに臨む。
詳細なレポートは此処では割愛しよう。
23日にもこの二次試験が用意されているようなので^^
夜は、提携先の方と会食。
3月下旬に社員旅行を企画しているとのこと。
一緒に来ないかとお誘いを受けるも、会議の日程と重なるんだよなぁ。
やるべきことが山積
午前中は、社内で人事内務。
午後から、東京へ。
小松空港へ向かう途中、異業種交流会ストローズ(STLOWS)の会員より、お電話を頂く。
1月23日(金)の新年会に、推薦したい会員がいるとのこと。
聞けば、よく知っている方なので、即了解。
新年会をメールにてご案内!
老舗企業の後継者たる会員が一挙に3名増加し、会員数も16名となった。
有り難いです^^
年間スケジュールの作成を急がねばならぬ。
夕刻より、組織再編案件の打ち合わせで、スキーム概要の骨子を決定。
もう一度、精査することとなる。
その思考を整理しているなか、先日、組んだ四半期決算数値が変更との連絡が携帯電話へ。
申告数値を変更するかどうか、重要性を考慮したうえで、明日、確認することとする(汗)
さて、「税理」の原稿。
事務局より、平成20年4月診療改訂後の影響(平成19年4月と比較)の数値比較が、遅延のお詫びと共にメールで届く。
うむむ。。。
締め日が近づいているのにもかかわらず、書くべき内容が増えた^^
盟友「かっちゃん」に相談せねば。
さらに、明日、認定登録医業経営コンサルタント「情報化認定コンサルタント」二次試験。
資料を読み込むも、未だ理解できず。
やるべきことが山積み^^
「ヘルプ ミー」(笑)
動機づけ
昨日のブログで、「モチベーション」につき記述した。
職業会計人のカリスマ、岩永先生の今回の考える言葉も「動機づけ」。
どのような切り口で語るのだろうか。
楽しみである^^
動機づけ(H21.1.19)
前回の“考える言葉”シリーズで、「リーダーシップの本質は“動機づけ”だ」と述べたがその“動機づけ”について考えてみたい。
広辞苑によると、“動機づけ”(motivation)とは「人間や動物を行動に駆り立てること。内部の動因と、外部の触発因との統合によって行われる」とある。
人間の行動を駆り立てる「内なる動因と外なる触発因の統合」の最大の要因を端的にいうと、それは「出逢い」でなかろうか。
少し、自分の歩んできた人生を振り返ってみよう。何か新しいことへチャレンジしようという気持ちになって、行動を起こしたとき、その呼び水となった「出逢い」がなかっただろうか。私が今の職業を選んだのは、下宿先でCPAを目指していた先輩との出逢いであったし、今日至っている仕事のレベルは、その節々における数々の「出逢い」とその後の関係性のあり方に負うところが多い。だから私は、「人の運命は、出逢いによって決す」(経営人間学)という言葉を信じている。
優れたリーダーは、人の心を動かすという。人の情熱に火をつけ、その人の中にある最高の力を引き出すことができる人こそが、真のリーダーであるといえよう。“動機づけ”は、リーダーの最も大切な仕事なのだ。
A・マズローは、人間の動機(欲求)には5段階(①生理的、②安全、③所属と愛、④承認、⑤自己実現)があると考えた。そして、①~④までの欲求を「欠乏動機」として、⑤の自己実現欲求を「成長動機」として捉えた。
21世紀の経営テーマである「自己革新」を推進するリーダーの“動機づけ”は、自己実現という「成長動機」に焦点を当てるべきだと考えている。なぜならば、自己実現という「成長動機」のみが、自らを完成させ最善を尽くそうとする働き、すなわち、セルフモチベーションを確立させ、組織のあらゆる階層で、リーダーシップを発揮できる人材が育つ文化を培ってくれるからである。
人間の成長には、二つの側面がある。一つは、能力的な側面であり、もう一つは価値観的な側面である。能力の成長とは、物事を処理する知識や技術を習得することである。一方、価値観の成長とは、物事の本質を深く考えることができる思想を身につけることである。
実は、マズローのいう自己実現欲求による“動機づけ”は、思想学習による価値観教育が前提にないと、成立し難いと考える。しかも、思想には位相(レベル)があり、経営人間学講座でいう「統合の思想」において他にないのではないだろうか。
次回は、“動機づけ”に深く関わる価値観について考えてみたい。
モチベーションとプレゼンテーション
一昨日の夕刻、大阪から金沢駅に着くや否やお客様のところへ直行。
経営者の方から、貴重な経営のアドバイスを頂く。
社員満足が8の会社は、お客様満足は8未満。
自分が満足できないにもかかわらず、それ以上にお客様を満足させることはできない。
経営者の仕事は、社員に対して、テンションではなくモチベーションを上げることだ。
テンションとは、上がれば下がる。
賞与の一時支給などがその例だ。
しかし、モチベーションは上がればなかなか下がらない点が違う。
モチベーションとは、リーダーがいかに職場で自己実現できるか社員を導くこと。
モチベーションを上げるためには、経営者のプレゼンテーションは必須のスキル。
ここで、プレゼンテーションの重要性につき、以前よりその経営者にご教授頂いていた。
来週、1月23日(金)の異業種交流会ストローズ(STLOWS)新年会は、恒例の自社の経営計画プレゼンテーション。
全会員の前で、一人15分間、今年の経営方針を発表する。
いかに、社員をモチベートするか。
そして、経営者の哲学、人生観すべてがその内容、話し方ににじみ出る。
さて、昨日は経営会議。
長期的に事業発展する仕組みを皆で考える。
脳脊髄液(のうせきずいえき)一滴を振り絞り、考え抜かねばならぬ。
とくに、この時期、じっくり考えてから行動しなければ、ロスが拡大する。
午後から、お客様のところで申告作業。
別表調整が難航し、お暇する時間が午後9時を越えてしまった。
疲労の中にも、働ける場所の有り難さに感謝しつつ、帰路へ着いた。
企業再生の概要
日本M&Aセンター大阪支社へ向かう。
梅田の中心、ブリーゼタワーへ。
(大阪支社長と女性スタッフと)
M&Aの専門家に企業再生の概要につき尋ねる。
倒産件数が増加しているため、企業再生案件が多いと理解していた。
専門家にこの点を尋ねると、増えていないとの答えであった。
まず、突然死が多いとのこと。
6月まで順調であったけれども、9月から売り上げが半分となるなど。
再生の暇がないので、再生の準備期間が整わないようだ。
また、民事再生費用にはお金がかかる。
弁護士報酬や財務調査費用のアベレージは約2,500万円。
その原資すらない場合、企業再生は難しい。
個人破産の場合でも、アベレージ250ー400万円かかる。
さらに、サービサーの債務の考え方をご教授いただく。
フリーキャッシュフロー(FCF)の10倍が返済可能と判断している。
FCFの10年分は返済可能。
それを越えるものは、サービサーへ売却と考えている。
創立30周年記念パーティーに参加
う~。
昨夜は久方ぶりに飲み過ぎてしまった。
昨日は、大阪の大手会計事務所の創立30周年記念パーティーに参加させて頂いた。
理事長先生から何かとご教授頂く。
100年に1度の不況と呼称される今。
これまで、先生は、銀行から「借金はするな」「できる限り返済せよ」と指導してきた。
しかしながら、今年に限って、得意先倒産に伴う貸し倒れリスクに備え、できるだけ借り入れをして資金に余裕を持つこと。
そして、嵐が過ぎたら返済すればよいと御指導いただく。
また、こういう時こそチャンスがある。
優秀な人材を雇用できる機会がある。
2009年は「準備」の年と捉え、2010年度に飛躍しよう。
素晴らしき教えであった^^





