 北陸税理士会の2月号会報誌への寄稿文です。
北陸税理士会の2月号会報誌への寄稿文です。
1月15日10時から税理士会館において、石川税理士碁友会が開催された。
当日は、囲碁サロン「石心」の佃優子師範をゲストに迎え、ハンディ戦の熱戦が繰り広げられた。
平成7年1月から開催されている石川税理士碁友会は、今回で41回を数え、平成最後になるかも知れない大会で優勝できたことは光栄なことであります。
四段で参加して、佃優子八段(師範)、北村四段、小倉三段、亀田五段との対局で3勝1敗。
碁友会には初回から参加して24年の歳月が流れた。
優勝の記憶を思い返すに。
1回目…二段で平成17年1月の14回大会。
2回目…三段で平成20年7月の21回大会。
今回の優勝は10年ぶりとなった。
ルールにより次回から五段となり、厳しい手合いが待ち受けますが楽しみながら参加したい。
囲碁は父親の影響で高校生あたりから興味を持ったが、これまで趣味として続けてきて良かったとつくづく思う。
将棋は62年ぶりに最年少棋士記録を更新した14歳の藤井聡太七段が注目を浴びましたが、囲碁も囲碁最年少の10歳でプロ入りした仲邑菫さんが脚光を浴びています。
囲碁は右脳と左脳をバランス良く使って、年令・性別・国籍・職業・肩書を超えた交流が楽しめます。
お誘い合わせてのご参加をお薦めします。
むすびに、お世話いただいている幹事の池田勝治先生、小川洋巧先生、小倉隆先生に感謝いたします。
(寄稿文、終わり)
石川県の囲碁界では、能美市出身の寺田柊汰(しゅうた)さん(21歳)が昨年12月9日に日本棋院中部総本部が実施した棋士採用試験で6人のうちトップの成績で唯一の合格者となった。
囲碁のプロ棋士試験には年齢制限があり、4月のデビュー時に23歳未満であることが条件で、寺田さんは最後のチャンスだった。
一昨年は本戦で1位だったものの、予選順位の関係で次点となり涙をのんだ。
寺田さんは辰口中1年時にプロを志し、日本棋院関西総本部の院生になっていた。
石川県出身のプロ棋士の誕生は2007年の田尻悠人四段以来12年ぶりとなる。
昨年12月30日に白山クラブでお会いしたが、将来有望な好青年だった。
今後のご活躍に期待しております。
写真…石川税理士碁友会でのスナップ。

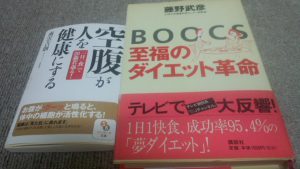
 新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
 皆様、2018年もお世話になりまして感謝しております。2019年も宜しくお願い致します。
皆様、2018年もお世話になりまして感謝しております。2019年も宜しくお願い致します。 平成最後の2018年を振り返る。
平成最後の2018年を振り返る。
 2018年、平成最後の忘年会の場所は、「鶴仙渓」の川沿いに佇むRoyal Hotel 山中温泉河鹿荘。金沢の会社から高速道路を使って約70分の場所にあります。
2018年、平成最後の忘年会の場所は、「鶴仙渓」の川沿いに佇むRoyal Hotel 山中温泉河鹿荘。金沢の会社から高速道路を使って約70分の場所にあります。