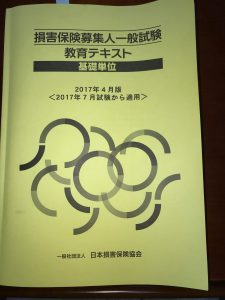12日(金)の朝、起きて外の景色を覗くと、銀世界。
暖冬が続いて、此処金沢が雪国であることをすっかり忘れていました。
その日は、雪没した車を横目に会社まで歩きました。
会社に着くと誰もいない。
始業まで電話番をするという貴重な体験をしました。
大雪で会社の機能もストップ。
初めて、業者の方に会社の駐車場の除雪を依頼しました。
コントロール出来ないものの一つが自然ということを思い知らされました。
さて、バートランド・ラッセルという方の話をします。
この方の亡くなった1970年に私が産まれています。
ちょっとしたご縁を感じます。
著書『社会改造の原理』(Principles of Social Reconstruction, 1916)の中で、人間の衝動には、所有衝動と創造衝動の2つがあると言っています。
所有衝動は、他人と共有することができないもの。
蓄財といった行為でしょう。
創造衝動は、知識とか芸術、善意といったように、私的に所有することなどのない価値ある何物かを世界にもたらすこと。
最良の生活とは、その大部分がさまざまな創造衝動に基づいて築かれた生活であり、一方、最悪の生活とは、その大部分が所有欲に発しているような生活であると喝破しております。
創造衝動で生活しているかどうか。
雪の中、自問自答しております。




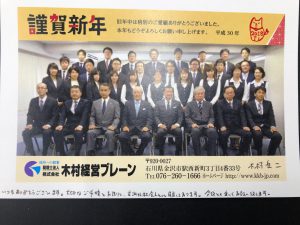 皆様、2017年もお世話になりまして感謝しております。
皆様、2017年もお世話になりまして感謝しております。