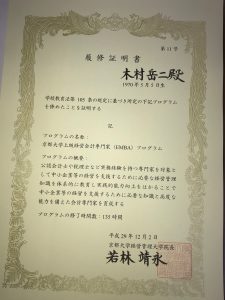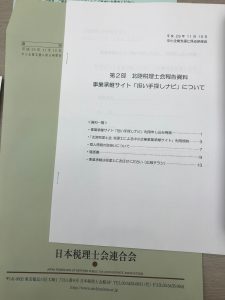「週刊エコノミスト」(11/28)の特集が目を引き購読した。
記事はセンセーショナルである。
〇、クラウド会計ソフトが大旋風、AI取り込みが死命を制す。
〇、税理士が足りない!約33,000会計事務所(税理士数は平成29年3月現在、76,000人)のうち上位2~3割は深刻な人手不足と値引き合戦。
税理士のタマゴの減少(2015年の合格者数は835人)が人材不足に拍車。
官公署退官者などを含めた税理士の新規登録者数は年間2,700人~3,000人だ。
AI時代に向け二極化が始まった。
〇、伸びる会計事務所も登場、先生商売から経営・税務コンサルへ。
〇、会計事務所と企業の経理部門。
「消える業務」…領収書の整理、ファイリング業務、単純な入力業務、預金通帳の記帳、請求書の発行・郵送、売掛金・買掛金の消し込み、現金による経費精算、小口現金と出納帳、記帳代行。
「残る業務」…財務諸表の分析、経営計画書の作成、税務申告、会計ソフトの選定、請求書・領収書の精査、業績予測などのコンサルティング業務、不規則な伝票処理、不正への検閲業務、資料作成の指導と提出の督促、。
〇、公認会計士(平成29年10月現在会員数、36,000人)の不足が仕事のブラック化を招く。
志願者の低迷は既得権益への固執と機械化の不徹底にある。
AIを駆使すれば再び創造的な人気業種に生まれ変わる。
〇、既存の会計ソフト業界(TKC、弥生)に対し、新興のクラウド型ソフト(フリー、マネーフォワード)が挑む構図だが、TKCもクラウド化を進めている。
クラウド型会計ソフトの導入は豪州69%、英国65%、米国40%と進んでいるが日本は14%と世界から遅れをとっている。
会計人はAIの影響を受けることは間違いないが、今後は経営コンサルや相続、事業承継、企業の合併・買収など様々な新しい仕事を付加価値にすれば生き延びる。
写真…金沢駅東口にて(12/2)。