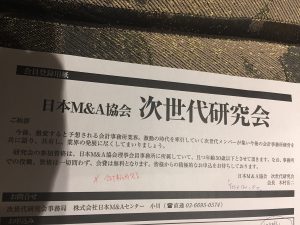 過日、日本M&A協会理事総会において、次世代研究会を発足致しました。
過日、日本M&A協会理事総会において、次世代研究会を発足致しました。
人工知能(AI)やマイナンバー制度という外部環境に加え、税理士試験受験者の減少、人的資源の充実など多くの課題が山積しています。
このような課題を会計人が一人背負うことなく、次世代研究会において、互いを鼓舞していき、課題解決することとしました。
では、どうやって。気合いと根性で、ダンベルを上げて体力勝負でいくか。それも大事ではありますが、医学の世界にヒントがあるのではないか。そんな考察をしている第一人者が、京都大学大学院(経営管理大学院・経済学研究科)の澤邉(さわべ)教授。(会議の席も隣で、夜遅くまでご一緒させていただいた。)
医学の世界は、研究者・臨床家・専門知識の再生産機能がしっかり働いている。医学(理論)を学んだドクターが医業の現場で治療・研究を行い、それを学会で発表し、その学会研究でさらに発展している現状がある。医学で社会貢献をしており、人命を救うことが社会的使命となっている。
医学の世界は、抽象(医学、理論)と具体(治療)を高速で行き来し、その交差点が学会という場所になっている。学会は、知識統合の場として、きちんと機能している。翻って、会計業界はどうだろうか。
会計の世界は、抽象(会計理論)と具体(会計実務)の行き来はなく、互いに独立している。そこで、理論を学んだ会計人が、企業経営の現場で実践を行い、それを学会の場で、コンサルティングによる成果を発表する。学会を理論と実務が行き来する連結環、知識統合の場所にできないか。
上記のとおり、京都大学大学院の澤邉先生より、今後の会計業界のブルーオーシャンは、医学の世界に大いなるヒントがあるとご教示頂く。
久方ぶりの洗練されかつ研ぎ澄まされた怒涛の知性に感化され、知的興奮マックス。血沸き肉躍る状態となりました。今後は、このような視点で、ダンベルを上げつつ、有り余る体力で戦略的に事業承継に取り組ことをお誓いし、やや長文となりましたが、今回の次世代発足式の感想とさせていただきます。


 書斎にいる時間は、パソコンとアイパッドにて、専ら、新聞や雑誌を含む読書と映画鑑賞を楽しんでおります。
書斎にいる時間は、パソコンとアイパッドにて、専ら、新聞や雑誌を含む読書と映画鑑賞を楽しんでおります。
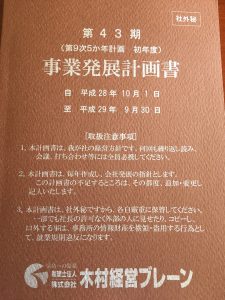 第43期事業発展計画書が完成し、全社員に配布しました。
第43期事業発展計画書が完成し、全社員に配布しました。
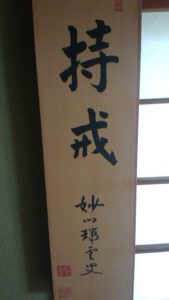
 過日、第43期事業発展計画発表大会で全社の方針を確認しました。
過日、第43期事業発展計画発表大会で全社の方針を確認しました。 北國がん基金、北國愛のほほえみ基金にそれぞれ20万円づつ、合計40万円を寄託させていただきました。
北國がん基金、北國愛のほほえみ基金にそれぞれ20万円づつ、合計40万円を寄託させていただきました。 7日、標題による金沢経済同友会のシンポジウムが開催され参加した。
7日、標題による金沢経済同友会のシンポジウムが開催され参加した。 第8次5か年(2012-2016.9)の5年の事業発展計画書をざーっと読み返すと、この5年間も多くのことを経験致しました。
第8次5か年(2012-2016.9)の5年の事業発展計画書をざーっと読み返すと、この5年間も多くのことを経験致しました。