7月30日(土)、中央大学学員会石川支部の総会、懇親会が金沢東急ホテル5階にて、実施されます。
今年の学術講演会講師は、メディアでも活躍している野村修也先生。
テーマは、「FinTech(フィンテック)とは何か-暮らしを変える金融技術の最前線-」です。先輩方にもわかりやすく好評なので、期待しております。
石川県支部の事務局を預かってはや数年。1400名超の同窓メンバーに郵送して返送されるのは200名超。参加が100名弱。最近は、知り合いの横展開でとくに若い方のメンバーも増加しております。
7月30日(土)、中央大学学員会石川支部の総会、懇親会が金沢東急ホテル5階にて、実施されます。
今年の学術講演会講師は、メディアでも活躍している野村修也先生。
テーマは、「FinTech(フィンテック)とは何か-暮らしを変える金融技術の最前線-」です。先輩方にもわかりやすく好評なので、期待しております。
石川県支部の事務局を預かってはや数年。1400名超の同窓メンバーに郵送して返送されるのは200名超。参加が100名弱。最近は、知り合いの横展開でとくに若い方のメンバーも増加しております。
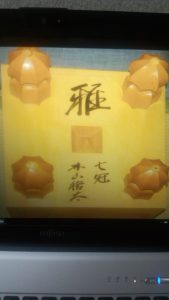
囲碁で史上初の全七冠同時制覇を4月20日に達成した井山裕太碁聖(27)に村川大介八段(25)が挑む第41期碁聖戦の5番勝負第2局は7月18日、金沢市の北國新聞会館で行われ、150手で白番の井山碁聖が中押し勝ちして2連勝となり、名誉碁聖がかかる5連覇にあと1勝とした。
井山七冠は鋭い大局感で村川八段に地を与えながらも最後に白の大模様に入ってきた黒石の生きを許さなかった。
「肉を切らせて骨を断つ作戦でリスクが大きく、普段はあまり選択しない。決断の時でした」と左辺の攻防について振り返っている。
7月2日にザ・リッツ・カールトン大阪で開催された「井山七冠のお祝いと師匠の石井邦生九段の千勝達成祝いの会」にも参加してきたが、約500名のファンが集まり井山七冠の人気の凄さを目の当たりにした。
6月16日には「内閣総理大臣顕彰」を安倍総理から受けている。
そのお祝いの会で、「井山と石井のトークショー」が佃亜紀子五段の進行であったが、私が興味を引いたのは井山裕太七冠の話。
「プロがいくつかの選択肢からこれまでの経験で先に外している手を、私はその手が有効でないかさらに考えている」と。
前17日に金沢市内のホテルで前夜祭があり、140人の囲碁ファンのうち約30人が高校生以下だった(北國新聞)。
子供の質問に答えた井山碁聖は、5歳のときにテレビゲームの囲碁に興味を持ち自然と囲碁の世界に入ったと語った。
その前夜祭の前に北國新聞会館で「対局室検分」が行われた。
「対局室検分」とは対局前日に、対局室の様子を確認すること。
ライト、空調、備品(座布団の厚さ、座椅子、ゴミ箱、ポットなど)そして、碁盤や碁石の打ち心地を確かめる。
今回の碁聖戦では、お声がかりもあり、碁盤と碁石を私が提供することになった。
「対局者と参加棋士および主催者の事前打ち合わせ会」、「対局室検分」、「局後の打ち上げ会」にも碁盤提供者として出席にあずかる。
局後の打ち上げ会で、井山裕太棋士から4年前に指導いただいた対局の写真が載っている私の叙勲受章記念誌を進呈した。
また、石川県が45年ぶり(この碁聖戦の立会人をつとめた本田邦久九段以来)に生んだ田尻悠人四段(25)とも親しくよもやま話をさせていただいた。
碁盤と碁石は、6月1日に大阪の井上一郎製作所へ佃優子師範と訪れ、佃亜紀子五段にも立ち会っていただき購入した。
碁盤は6寸8分厚(7寸盤だと高くなるので少し低く)の追柾目。
とくに碁石が厚いのは好まない棋士がいると亜紀子五段からアドバイスがあり33号厚を選んだが気に入ってもらったようで良かった。
佃姉妹先生のご指導の支えにより検分は無事に終わった。
そのあと、碁盤裏に井山裕太七冠より揮毫をいただいた(写真)。
揮毫に使う筆と墨を準備するのに苦心した。
結局、井山七冠は数本の中から中筆を選び、墨は自宅近くの書道店で買った「木簡墨」がうまく合ってほっとする。
大盤解説会では林漢傑(りんかんけつ)七段と佃優子アマ六段が多くの囲碁ファンに5時間もの長時間、分かりやすく多岐にわたる楽しい話題で解説していただいた。
碁盤と碁石はこのタイトル戦が初使用だとご紹介いただく。
熱戦から一夜明けた19日、井山碁聖は金沢市本多町2丁目の日蓮宗「本行寺(ほんぎょうじ)」を訪れ、江戸時代前期に活躍した棋士の本因坊算砂(ほんいんぼうさんさ)日海上人の碑を参拝した。
算砂は七大タイトルの一つ「本因坊」の由来である本因坊家の初代家元で、加賀藩3代藩主前田利常が金沢に招いている。
本因坊算砂は(1559~1623)1578年に織田信長に「そちはまことの名人なり」と称揚され、これが現在も各方面で常用される「名人」という言葉の起こりとの説がある。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康ともに算砂に対し五子の手合い割であったと「坐隠談叢(ざいんだんそう)」にある。(坐隠は広辞苑で見ると囲碁の異称だと初めて知った。)
本因坊道策は算砂没後22年後に生まれ、本因坊秀策は道策没後127年後に生まれている。
辞世の句は、「碁なりせば刧(コウ)なと打ちて生くべきに 死ぬるばかりは手もなかりけり」
もっともであります。
井山裕太七冠は先月6月30日に本因坊戦5連覇で二十六世永世本因坊の資格を得た。
算砂没後393年、秀策没後154年に永世本因坊になった27歳の天才棋士井山裕太七冠を誇りに思うとともに日本を背負って世界で活躍して欲しいと願っている。
写真…揮毫いただいた初舞台の碁盤
事業承継相談の現場で、とくに財産権の承継でよくある誤解があります。
自社株と会社への貸付(会社からすると借入金)は、相続財産の対象外という誤解。自社株式と会社への貸付金は、もちろん、相続財産の対象です。
経営者の方に聴いてみると、創業の時に出資しているので、随分昔のことだから、忘れているという方が半分。覚えているけれども、返済を期待していない(会社からすると、返済義務がないので、負債ではなく、資本・純資産であるのだが!)ので、寄付している感覚という方が半分くらいだろうか。
ところで、この誤解をなぜ会計事務所のような専門家が放置しているのかを考察してみました。結論はこうです。会計事務所にとっては、あまりにも常識すぎて、経営者の方に伝えていないのではないか。会計事務所の常識は、他の方にあっては非常識ということなのかなと。
自戒すると同時に、普段から、相談者の方に、承継について日常的に話していこうと思います。
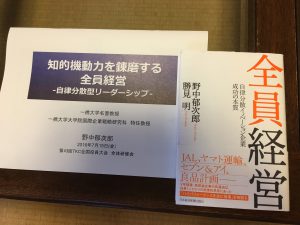 先日、第43回TKC全国役員大会全体研修会において、野中郁次郎教授の講演を拝聴する。
先日、第43回TKC全国役員大会全体研修会において、野中郁次郎教授の講演を拝聴する。
前日のゆずのゲリラライブ(生で栄光の架け橋を聴きました!)と同じくらい、感銘を受けた次第。
まず、経営者の思いや信念があります。全てはここから始まります。経営者の思いや信念は、「私はこう信ずる」という1人称の世界。
次は、役員、幹部、社員に伝える二人称の世界へと場所を移す。ここが重要で、キーワードは共感。「そうだー、これだー」と社員全員で共有できたとき、次のステージである仕組みへとつながる。伝える場所は、会議室なのか、移動中の車の中なのか。講演を聴いて改めて思い知ったのは、「計画書読んどいてー」は伝えるうちに入っていないということ。蛇足ながら、実務で実力のある野武士集団が、価値観を合わせ、ベクトルを統一化して、理念に突き進むと最強の組織が誕生すると思います。鍛えに鍛えたアスリートが理想に突き進む知的体育会系。これが最強の組織集団ではないかと。共感の下敷きは、価値観であり、社員全員が経営者が好む本を読む、あるいは映画を観ていると共感度合が高まるのではないかとも推察しています。
さて、最後の仕組み化、三人称への道が長くて遠い。経営者の思いを事業計画書に落とし込むことは簡単。魂の入っていない仏像は、いつの世も悲しい。社員に伝える二人称の世界がやはり重要だということを教えていただきました。

10日の参議院選挙開票で参議院の新勢力は与党146(+11)、野党96(-10)となった。
また、改憲勢力が全議席の3分の2超を占めた。
これで衆参両院で憲法改正の発議が可能となった。
今回の参議院選挙では、70年ぶりに選挙権年齢が18歳と19歳に引き下げられ、新有権者数は240万人も増えた。
政府は全高校生に副教材を配布するなど主権者教育や啓発に力を入れた結果、投票率は抽出調査で45.45%(18歳51%、19歳40%)となっている。
石川県の18歳と19歳の推定投票率は48.31%った。
全国の平均投票率は54.7%で過去4番目の低さだった。
石川県は56.88%。
日本国民であるのにも関わらず、投票しない人が半数近くいるのは驚愕だし、国民主権の放棄だと言われてもしかたない。
義務を行使しないで「ごたく」を並べて権利を主張する風潮は困ったものである。
企業においても同じだ。
選挙結果を受けて安倍首相はアベノミクスを一層加速すべく大胆な経済対策を実施すると表明した。
英国のEU離脱や円高傾向で景気の不透明感が増す中、零細・中小企業の対策にも万全を期して欲しい。
写真…朝顔(7/12小松にて)
 税理士法人木村経営ブレーンの設立が平成26年(2014年)10月ですから、もうすぐ第二期が終了しようとしています。また、ホームページが昨年(2015年)の6月に完成し、リニューアルしてはや1年が過ぎようとしています。月日の経つのは早いというのが素直な実感です。
税理士法人木村経営ブレーンの設立が平成26年(2014年)10月ですから、もうすぐ第二期が終了しようとしています。また、ホームページが昨年(2015年)の6月に完成し、リニューアルしてはや1年が過ぎようとしています。月日の経つのは早いというのが素直な実感です。
さて、2016年7月9日号の週刊ダイヤモンドで特集が組まれているように、落語に再び注目が集まっているようです。
私の好きな落語家は、古今亭志ん生(1890-1973年)。師匠の落語は、専ら移動中の車の中で聴いてます。師匠の本からも人生の大事なことを学びました。
①「びんぼう自慢」(酒もゴルフも全て人の角を丸くするための芸の修養)
②なめくじ艦隊(人前で話をすると、その人の生き方が出る)

6月25日~30日にカナダ最大の都市・トロント、世界三大瀑布のひとつ・ナイアガラの滝、モントリオールとケベック(世界遺産)をめぐる囲碁交流の旅に出かけた。
囲碁サロン「石心」の佃席主をリーダーに13名のメンバー。
カナダには2008年(H20年9月)に日本医業経営コンサルタント協会の海外研修でトロント小児病院、モントリオール大学病院などを訪れているので2回目となる。
カナダは日本よりマイナス13時間(サマータイム)の時差で昼夜逆転する。
体は時差の解消に一日一時間かかるそうな。
世界で2番目に大きい国土なのに、人口は東京より少ない3,600万人。
人口の40%はオンタリオ州(トロント)に集中している。
GDPは世界第9位(2010年)。
政体は立憲君主制で元首はエリザベス二世女王(イギリス)でデービッド・ジョンストン総督が女王の代行を務める。
首相はジャスティン・トルドー(44歳・自由党)。
カナダ憲法は1982年に施行され、二言語多文化主義・ケベック州の特殊性・原住民居留地の特殊性などが認められている。
旅行2日目…トロント大学囲碁チーム9名と対局、私は5番手で2段の方と対戦し2子局白番2目勝ちだった。
オンタリオ州トロントでは「CNタワー」(1976年完成553.33㍍)に上る。
2007年までの32年間、ドバイの「バージュ・カリファ」(828㍍)に抜かれるまで自立式建築物としては世界で一番高いタワーだった。
「東京スカイツリー」(2012年634㍍)も出来て世界三位になった。
今後、サウジアラビアでは「キングダム・タワー」(2018年完成予定1,000㍍超え)、ドバイでも2020年の国際博覧会に向けて「バージュ・カリファ」より1段階高いタワーが建築される
ナイアガラの滝は世界三大瀑布(他に、南アフリカ大陸のイグアスの滝、アフリカ大陸のヴィクトリアの滝)のひとつで、私は2回目になる。
エリー湖(北アメリカにある五大湖のひとつで)からオンタリオ湖に流れるナイアガラ川にあり、カナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨーク州とを分ける国境になっている。
カナダ滝は落差56㍍、幅675㍍、滝壺の深さ55㍍で轟音とともに水煙が絶えず、毎年数㌢浸食されている。
クルーズで滝の近くに行き、水しぶきを浴びながら、マイナスイオンを吸収する。
トロントはカナダ最大の都市で人口は250万人
首都はオタワ。
目につく表記はフランス語と英語が併記(二言語主義)されている。
カナダを知るには歴史を紐解かないと国情は分からない。
(1)、北ヨーロッパの漁業民(ヴァイキングと言われた)の北アメリカへの入植。
(2)、1497年にイギリス(ヘンリ7世)が派遣したイタリア人のカボットが「カナダ」発見。(1492年、コロンブスのアメリカ大陸発見)
(3)、1534年にフランスのフランソワ1世が派遣したジャック・カルティエがセントローレンス川流域を探検し、この地をカナダと名付けた。
(4)、1603年フランス・アンリ4世の時に植民地を成立させた。
(5)、イギリスは毛皮産地を占領すべくフランスと戦争。1763年のパリ条約でフランスはカナダ側の大部分を放棄し、これによりイギリス領カナダ植民地が成立。
(6)、1867年7月1日にイギリス領で最初に自治が認められカナダ連邦となる。
150年前のことである。
(7)、第一次世界大戦(1914~1919)にカナダはイギリス帝国の一員として参戦。それが認められて、戦後の1926年にイギリスはカナダに外交権を付与した。
(8)、1982年に独自の憲法を制定。イギリス連邦の一員でありながら、名実共に独立国家となっている。
しかし、依然としてイギリス二世女王を戴く連邦立憲君主制国家にとどまっているが、女王の代理であるカナダ総督も現在はカナダ人が就任しており、イギリスとの関係はまったく形式的なものになっている。
イギリス系住民とフランス系住民、さらに多くの民族(47民族:ウイキぺディア)が共存する多民族国家としての道を歩んでいる。
現在、20カナダドル紙幣にはイギリスエリザベス二世女王が印刷されているが、これも近々、カナダに貢献した女性カナダ人に変えるという。
1965年のモントリオール万博の頃からケベック民族主義(フランス系住民)が台頭し、1970年代にはケベック分離主義者のテロ活動が活発になったが、1980年と1992年の住民投票結果では、いずれも分離独立は否決されている。
ケベックシティはカナダの中でフランス語を第一公用語にしている。
そのため、ビジネスに英語を使いたいため経済の中心はモントリオールに移動し、ケベック・シティは行政中心である。
カナダの言語は英語57%、フランス語21%、その他22%になっている。
旅行3日目…ナイアガラを観光したあと、トロントからモントリオールへVIA鉄道(カナディアンロッキー観光に使われるジーゼル車)で移動。
17:00に出発したがハプニング発生。
モントリオールに21:42の予定で、その時刻あたりに停車した駅で降りたら、なんとひとつ前の駅(ドーテルイースト)だった。
車中で離れて座っていた3人は降りたらモントリオールでないことにびっくり、その駅からタクシーでモントリオールのホテルへ。
車中では何のアナウンスもなく、憤慨しても自己責任であとの祭。
旅行4日目…モントリオール観光を経てバスで世界遺産「ケベック・シティ」へ移動。
ノートルダム大聖堂(新大陸で最初に建設された聖堂)をはじめメキシコ以北で現存する唯一の城郭都市。
1985年に世界遺産登録。
カナダには、北米大陸の先進的なイメージを持っていたが、その歴史から複雑な国情があることを知った。
自動車は法律により昼もライトを点灯し、飲酒運転はおとがめなし。
消費税は約15%で、学費や保育所は安く医療費はタダ。
しかし、日本人ガイドが身をもって体験した話では、診療所から病院への紹介状をもらうのに3か月、自分で病院に電話して診療を受けたのが、さらに4か月後。
救急医療も7時間待ちでは助かる命も救われない。
薬で日本では禁止されているものがあるという。
長寿世界一を誇る日本の国民皆保険制度のありがたみを痛感する。
自然は豊富でホイールウォッチイングも9割の確率で楽しめる。
カナダの旅は歴史の変遷の痕跡を訪ねる旅でもあった。
写真…カナダ側からの「ナイアガラの滝」
 過日、北陸税理士会金沢支部定期総会(第36回)にて、従業員永年勤続表彰を頂く。当社幹部のN氏は20年表彰、T氏は10年表彰である。(写真は、寺田支部長から表彰を受けているT氏)
過日、北陸税理士会金沢支部定期総会(第36回)にて、従業員永年勤続表彰を頂く。当社幹部のN氏は20年表彰、T氏は10年表彰である。(写真は、寺田支部長から表彰を受けているT氏)
これからも宜しくお願い致します。
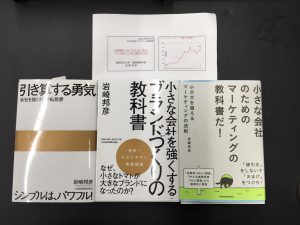 過日、静岡県立大学の岩崎邦彦教授の講演を聴く機会を頂き、早速、著作3冊を拝読。
過日、静岡県立大学の岩崎邦彦教授の講演を聴く機会を頂き、早速、著作3冊を拝読。
小が大を超えるには、尖るしかない。漢字が戦略を教えてくれる。小が大の上と書いて、「尖」る。
ホースの水を勢いよく放出するには先端を絞る。
これからは、商品やサービスを絞り、強みを尖らせていく。今回の教えを事業計画に反映していきたい。こう素直に感じた次第です。

6月16日(金)~17日(土)に(株)TKCの特別招待(全国から13名)を受けてTKC全国会理事会とTKCタックスフォーラムに出席させていただいた。
飯塚真玄取締役会長(私と2週間遅れの昭和18年2月5日生まれの73歳)のご子息、飯塚真規代表取締役専務(昭和50年3月生まれの41歳)に初めてお会いし挨拶させていただいた。
将来のTKCを背負って立つ方である。
(株)TKC出版の名誉会長である高橋貞夫氏もお元気で思い出話に花が咲く。
全国会顧問の三木武彦氏からも声をかけられた。
「木村さんと私は同じ昭和18年生まれです。気に掛けております」と気さくに会話していただく。
近畿兵庫会会長の稲田実氏、医会研代表幹事の海来美鶴氏、関東信越会の山崎好一氏(日本医業経営コンサルタント協会の栃木県支部長)にお会いする。
1、TKC全国会理事会
(1)、2014年~2021年の行動テーマ。
TKC全国会創設50年(2021年)に向けての統一行動テーマは、「Chance、Change and Challenge 未來を拓く。TKC会計人の新成長戦略2012!」である。
活動テーマは。
・第1ステージ(2014年~2016年の3年)
Chance…TKC会員事務所の総合力強化と会員数の拡大。
・第2ステージ(2017年~2018年の2年)
Change…事務所総合力を発揮し、高付加価値体制を構築!
・第3ステージ(2019年~2021年の3年)
Challenge…TKCブランドで社会を変える!
(2)、金融機関向けFinTechサービス
TKC会員が顧問先からの委託にもとずいて、信頼性の高い決算書・月次試算表等を定性情報と共に、OMSから金融機関に提供するサービスを10月から開始する。
全国には地銀、第2地銀、信用金庫、信用組合が529行あり、TKC説明会にすでに169行が参加予定である。
仕訳の4割を省力化…全仕訳の預金仕訳は38%、現金仕訳は29.3%、その他32.7%である。
今後、FXシリーズの新機能で仕訳の約7割を省力化…
銀行信販データ受信機能38%、現金証憑ストレージサービス(スキャン)27.2%、ネットレジ5.2%、PX連動3.3%、その他26.3%となる。
(3)、5月24日に「中小企業等経営強化法」が成立し、現在、7月1日施行予定で経産省が政省令を準備中。
法案のスキームは。
ア、事業分野別生産性向上方法の指針策定。
イ、経営力向上計画の認定(人材育成、財務管理、設備投資等に関して3~5年の計画を立案し、労働生産性(一人当たりの営業利益)の伸び率が2%以上の目標を認定の判断基準とする)
ウ、経営力向上計画の策定を経営革新等支援機関がサポートする。
(4)、相続税書面添付実践報告…平成25年分の国税庁発表
ア、被相続人数…126万人
イ、申告件数…7万件(うちTKC1万5千件)
ウ、税理士関与件数…6万3千件
エ、書面添付件数…約7,500件。
オ、書面添付割合…11.8%
カ、意見聴取割合…11.2%
キ、実地調査省略割合…37.9%
2、TKCタックスフォーラム2016
(1)、研究発表
「会社法からみた税法上の非上場株式の時価評価~事業承継の視点から~」
TKC中部会研究グループ10名の発表。
・提言…現行評価通達には多くの矛盾があり適正な時価を反映しているとは言いがたい。新非訟事件手続法による専門委員制度のような組織を創設したらどうか。
(2)、講 演
「社会保障と税の一体改革のグランドデザイン」
中央大学法科大学院教授 森信茂樹氏
・高齢者と勤労者の高所得者と低所得者それぞれの「あるべき再配分」が行われていない。
「税務行政の現状と課題」
国税庁課税部長 川嶋真氏
・実調率は国税庁職員数(5万5千人)の減少と申告件数の増加による業務量の大幅な増加、経済取引の国際化・高度情報化の進展による業務の質的困難化で法人は3.26%(30年に1度)、個人は1.1%(90年に1度)になっている。
・職員構成
40歳以下…38.9%
41歳~50歳…33.5%
51歳以上…27.6%
・女性は10,609人(約20%)
「国際課税の最近の動向」
国税庁長官官房国際業務課長 池田義典氏
・「パナマ文書」の流出により、国際的な租税回避や脱税、マネーロンダリングなどの問題が浮き彫りとなった。
2日間にわたる、理事会へのオブザーバー参加とタックスフォーラム研修は有意義だった。
写真…ユリ(6/16自宅)
 お電話でお問い合わせ
お電話でお問い合わせ