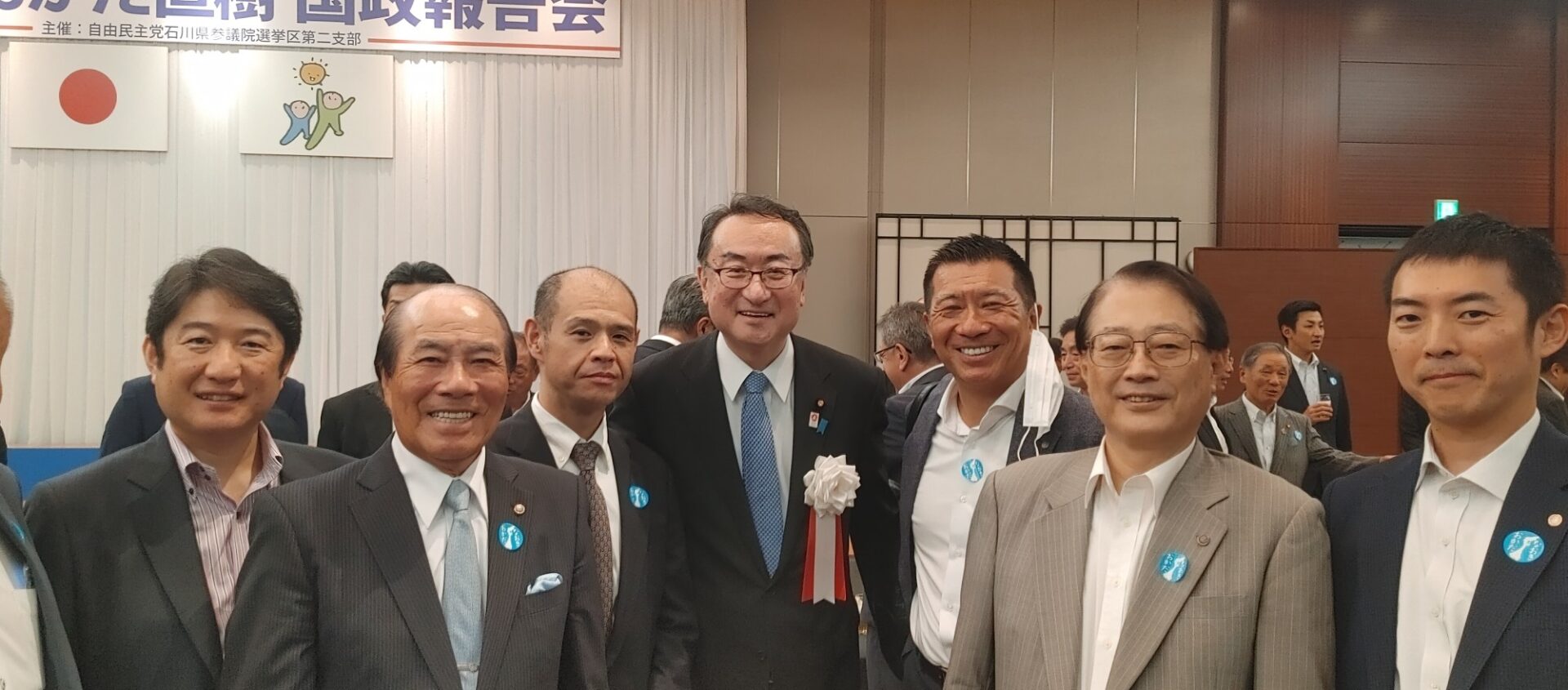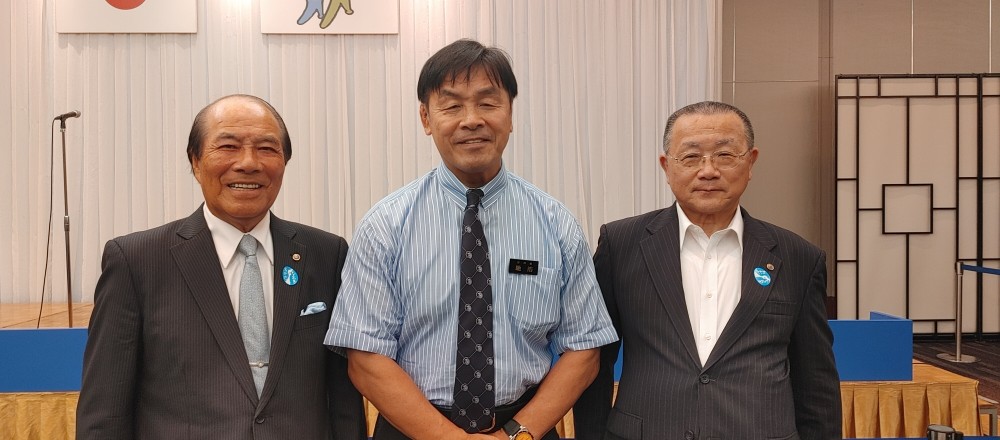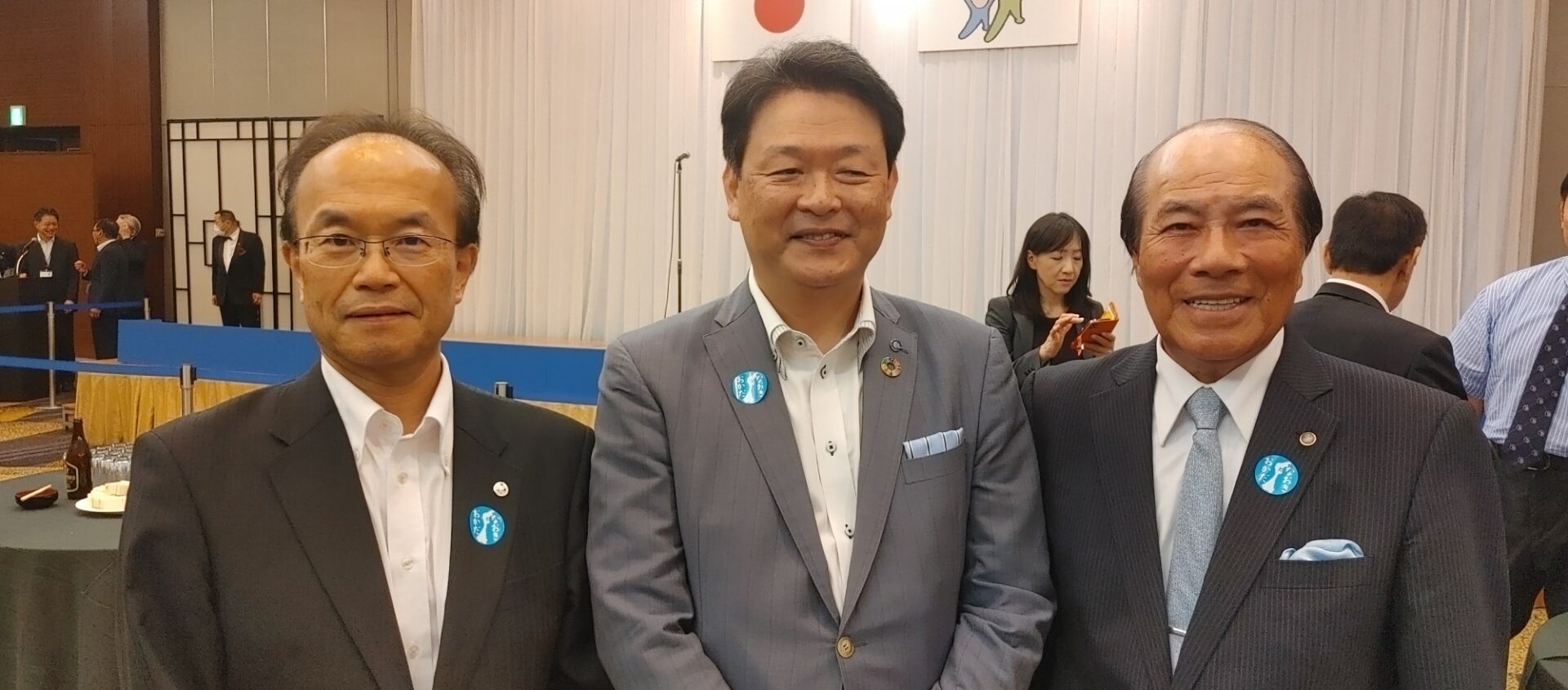私の使命は、木村経営グループの長期利益の実現であることから、2018年(平成30年)入社の方から、新人研修の講師を務めております。
多くの研修企画は、知識を新人には与えるが、グループの理念は誰も教えてくれません。
対象は、8名。
2023年(令和5年)入社4名。
2022年(令和4年)入社4名。
研修を終えた後の楽しみが、受講者のレポート。
すぐに私だけでなく全社員に対し、グループウェアによって共有されます。
受講者8名のうち、2022年入社のMさんのレポートが秀逸であったので、その抜粋を引用したい。
本日は木村社長による自創経営研修に参加させていただきました。
冒頭に社長がおっしゃった、「頼まれごとは試されごと」という言葉が非常に心に残り、私自身、「試されている」という意識があまりなかったと気づかされました。
自分は常に試されているという意識を持ち、来期から生産高測定者になる身として、より一層責任感を持って業務に取り組もうと思います。「今はまだ拡大業務よりも既存の巡回監査の徹底を」というお言葉をいただき、焦って拡大のことばかり考えるのでなく、今の自分にできる最大のサービスを提供することを考え、業務に励んでいきたいです。
そのようにしてお客様との信頼関係を築き上げた上で、ニーズに合った提案ができるようになりたいと思いました。
今回で木村社長による自創経営研修が最後となりましたが、計6回の研修を通し、この会社の歴史や目指していく像を理解することができました。
また、社長からも様々な心強いお言葉もいただきました。今後、何かに迷ったり躓いたりした際には、自創経営で学んだことを思い出して、乗り越えていきたいです。
本日は研修に参加させていただき、ありがとうございます。

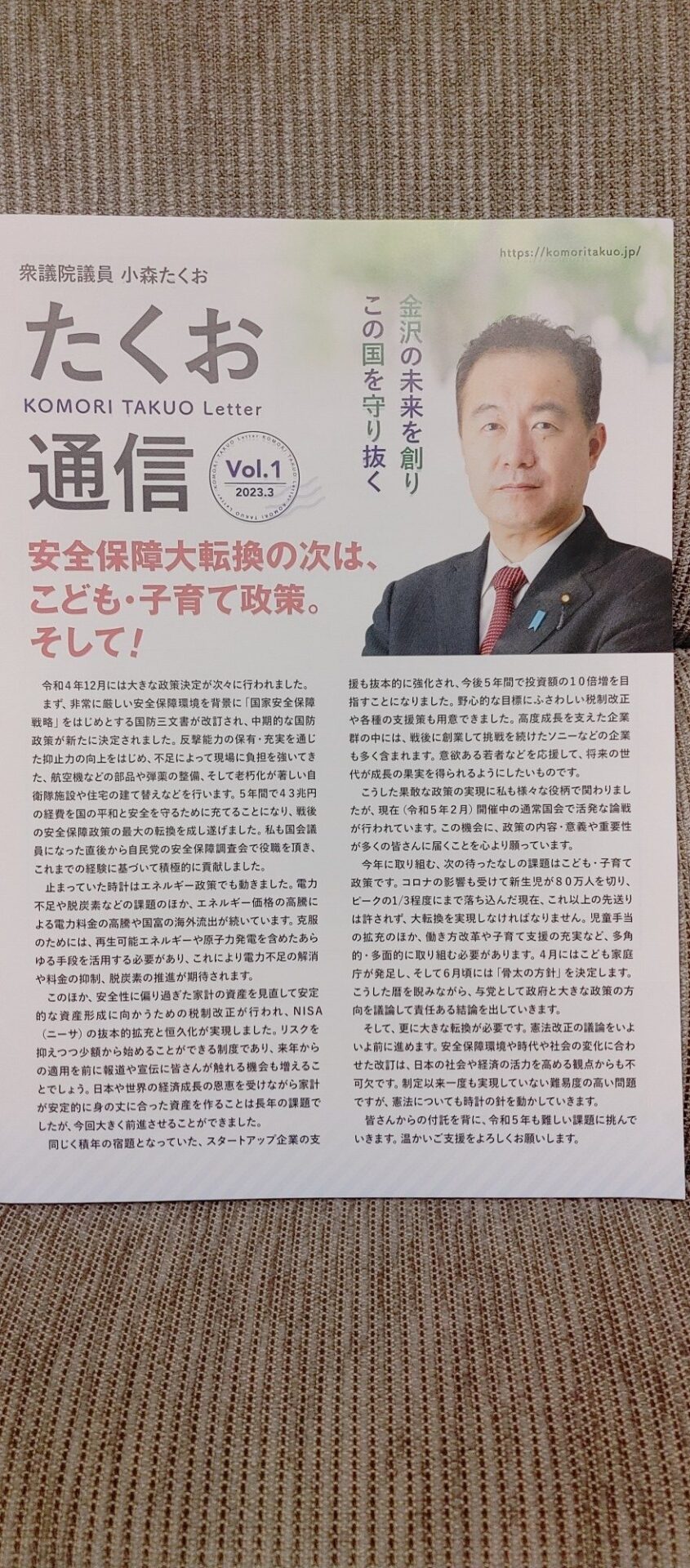

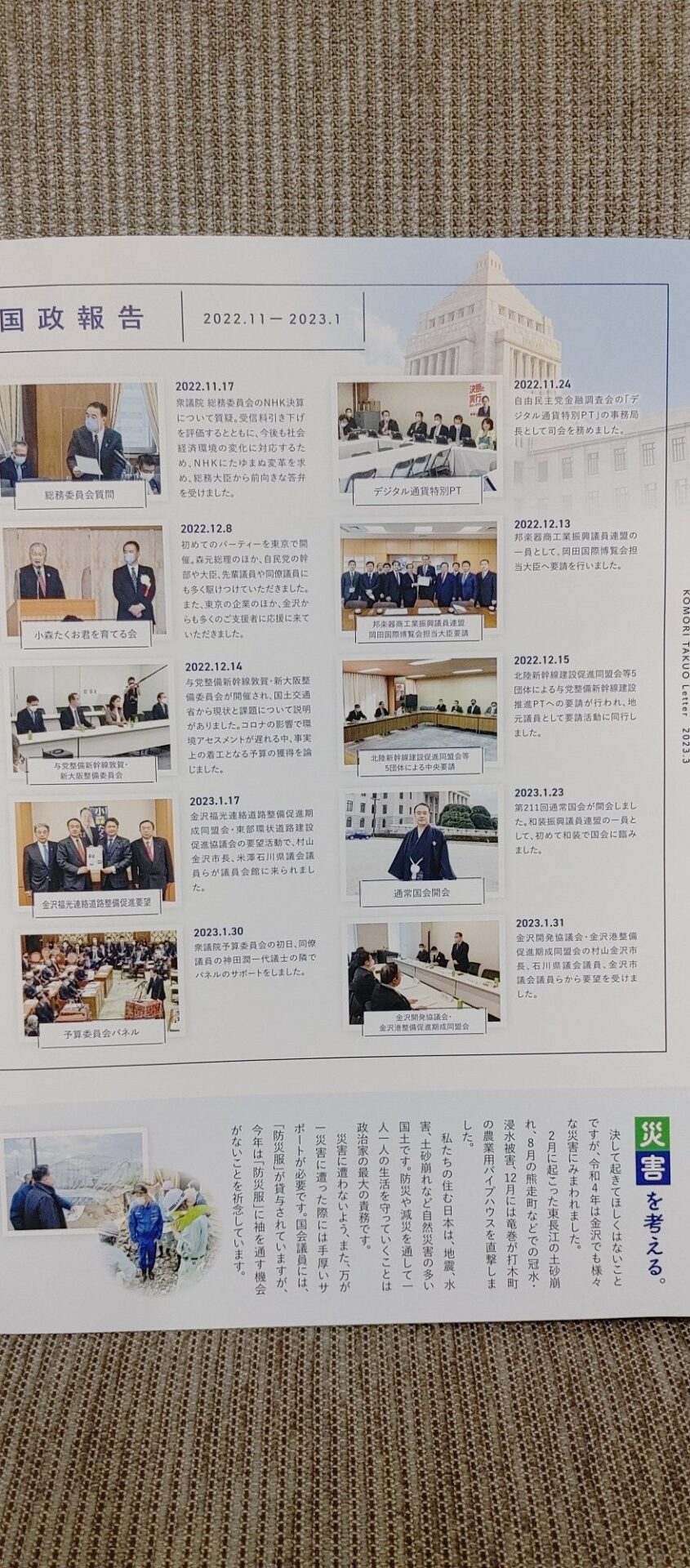
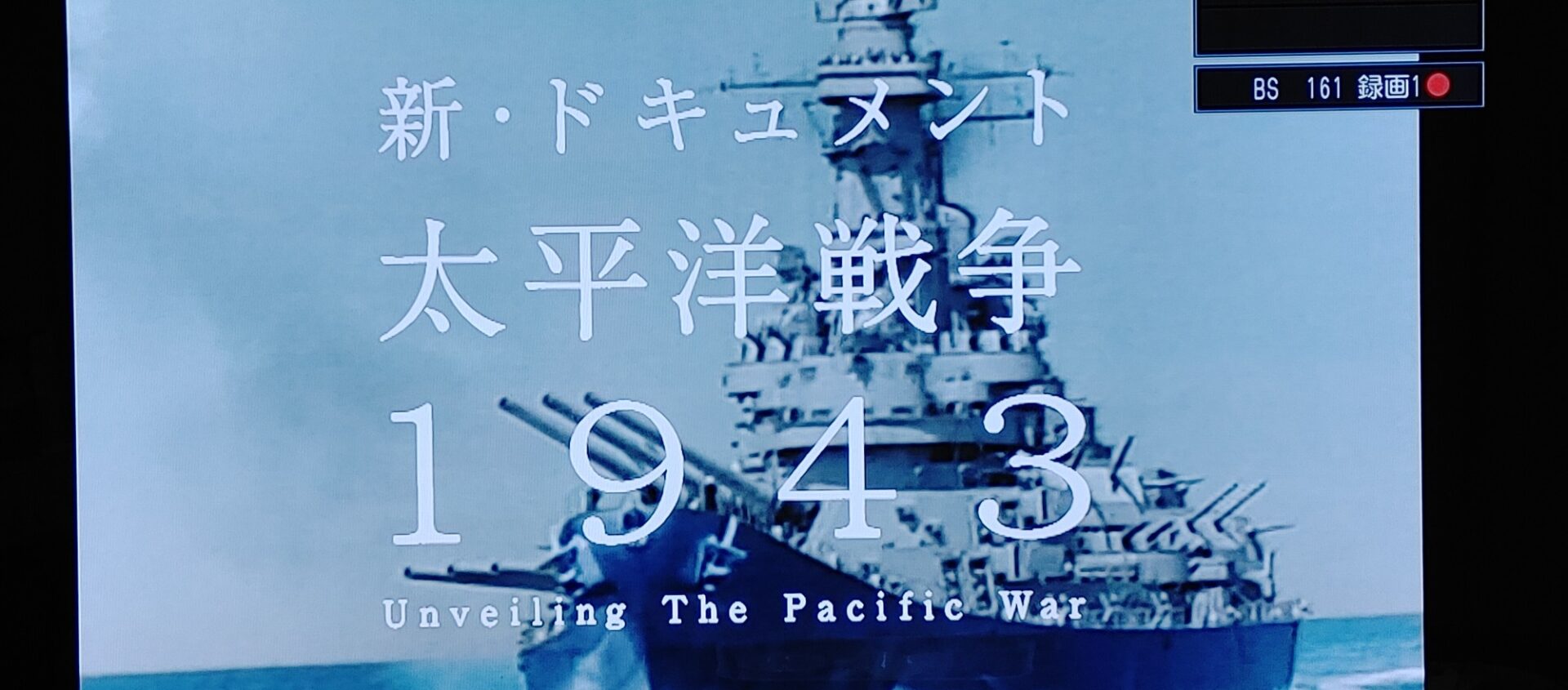
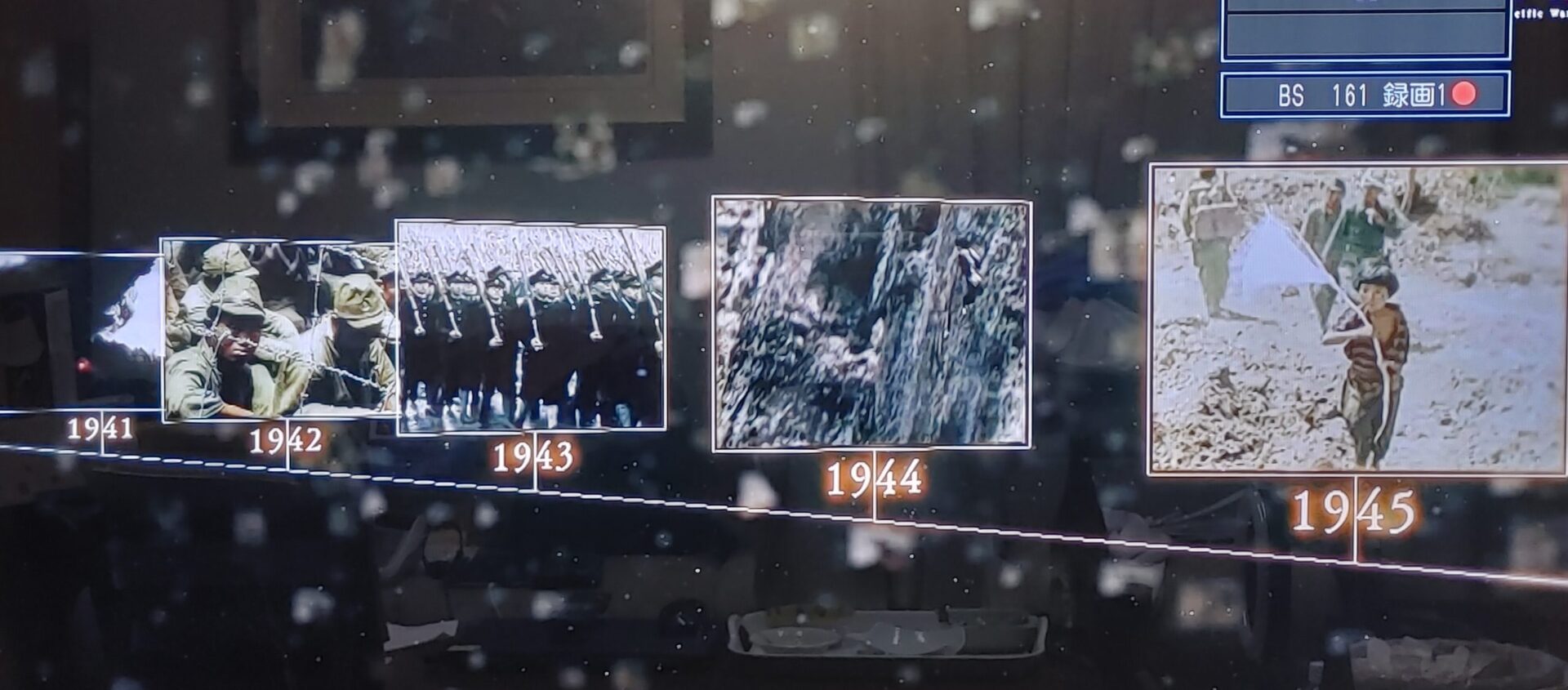








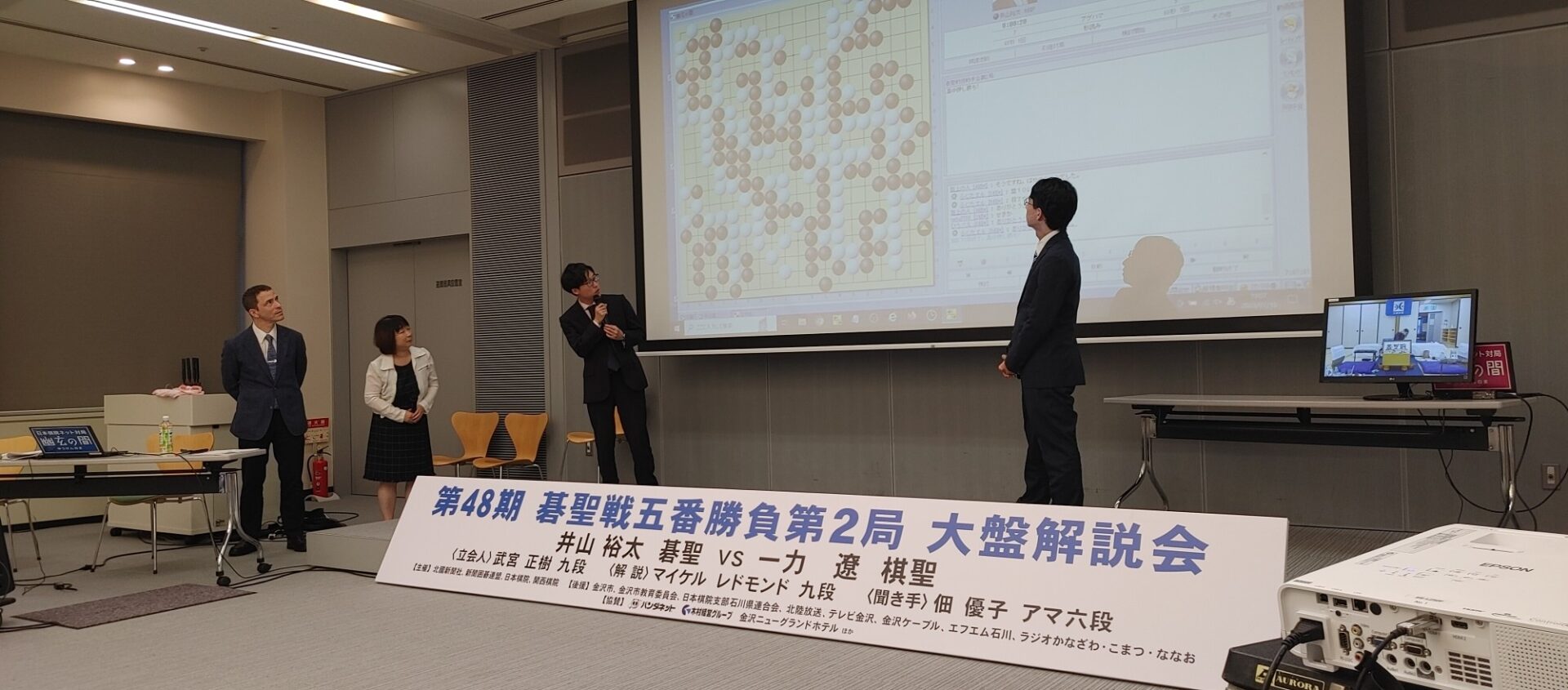
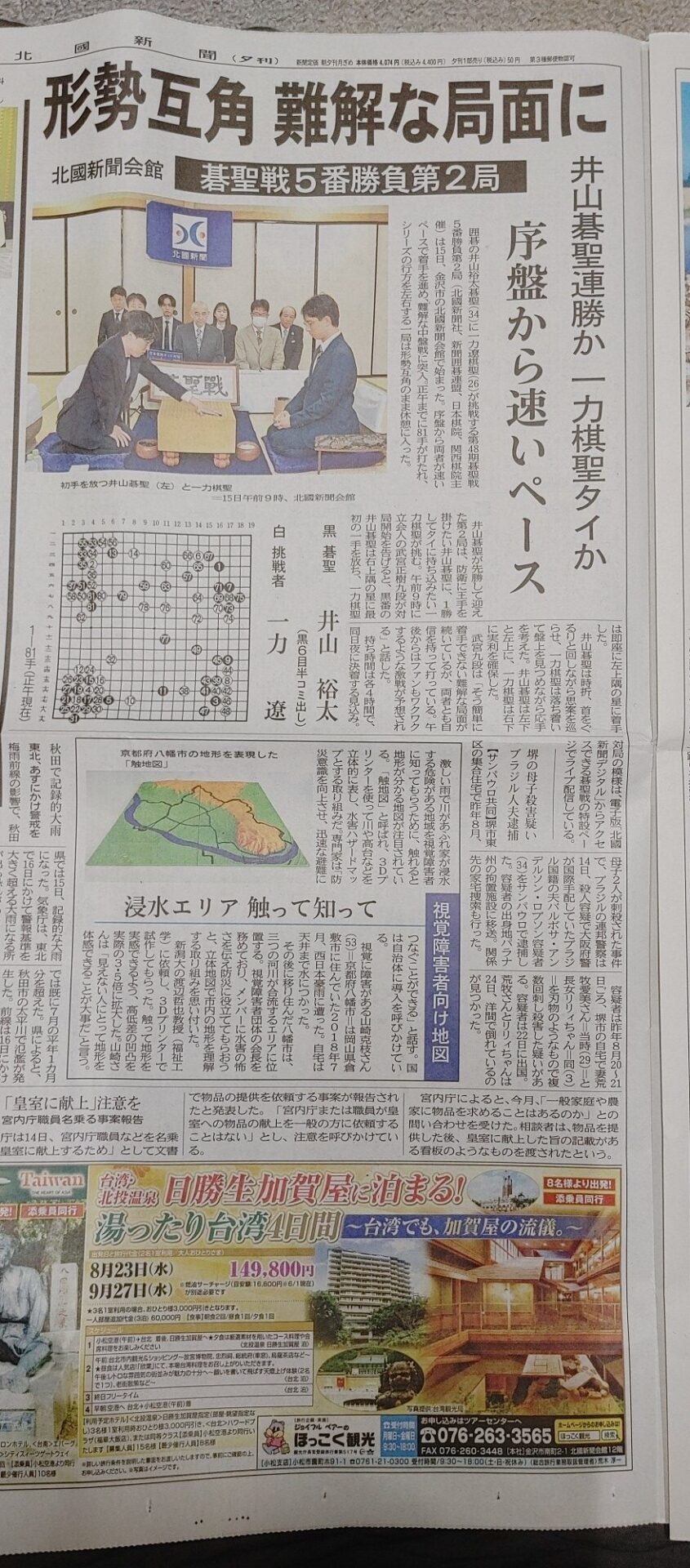

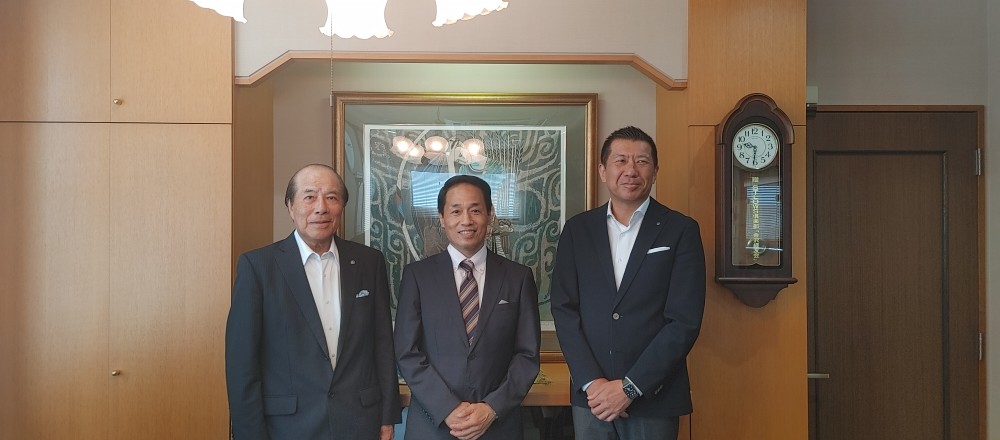
 過日、北陸税理士会金沢支部長の拝命を受け、北陸税理士会の会員広報誌の「おじゃまします 支部長さん」の取材に応じた。
過日、北陸税理士会金沢支部長の拝命を受け、北陸税理士会の会員広報誌の「おじゃまします 支部長さん」の取材に応じた。