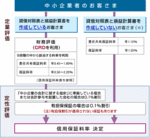今週のSTLOWS勉強会。
財務・税務シリーズで講師を担当する。
今回のテーマは、資金別貸借対照表。
sikinbetu.pdf
2003年に、古田土先生からご教授頂いてからずっと愛用している会計ツールの一つだ。
池永税理士の著作にも紹介されており、今回の講義で参考にさせていただく。

会社にお金が残る経営―決算書の意味がわからない社長のための (アスカビジネス)
- 作者: 池永 章
- 出版社/メーカー: アスカエフプロダクツ
- 発売日: 2005/02
- メディア: 単行本
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)。
短大の学生の中でも、「ちんしゃくたいしょうひょう」など言い間違えることの多い用語。
職業会計人ならば、何らかの資格試験の時からの付き合いだから、家族並みの親しさをもつ呼称であろう。
英訳して、Balance Sheet、略してBS。
ブリジストンというタイヤメーカーではない、一定時点の財政状態を表す財務諸表の一つ。
BSにこそ、経営者の経営姿勢、個性が現れる。
学生の頃から20年来お付き合いさせて頂いているBSにつき、今回、2時間ほどお付き合い頂きたい。