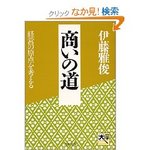現在、当社の専門コンサルティング部会(人事制度)が小冊子第二弾を推敲中。
1日1頁を目処に、更新していく。
目からウロコが落ちるほど簡単に人事制度を構築するためのブログ
金沢会計人 のすべての投稿
左前方の自転車
午前中、来客対応を数件させて頂いた後、金城短大へ。
朝方、雨を降らせていた雲が、国道8号線を白山市方面へ向かうにつれ、風に流されていく。
ちょうど晴れ間が見え始めた頃、目的地へと到着する。
「会計学総論」は、合同クラス90名、単体クラス25名。
お互い、気をつかう関係となり、授業にも協力的だ。
授業後、きんどん会メンバーであるT専務の会社へ立ち寄る。
その後、車を走らせていると、左前方に競技用の自転車で颯爽と走っている方がいる。
結構早いなと思いつつも、追い抜かす。
そして、信号待ちの時、ちらっと横顔を拝見すると、M柄氏。
「こんにちは!」と話かけさせて頂き、近くの喫茶店で近況を語りあう。
なんと奇遇なことだろう。
社長就任して数ヶ月間のことを、端的にご報告申し上げる。
最近、ヒントを得て、何事も万事急がないこととした。
話し方、歩き方、あらゆる動作を緩慢とした結果、時間という犠牲を払っているおかげだろうか、発見がある。
「泰然自若」として、とにかく急がない。
商いの道
伊藤 雅俊著「商いの道―経営の原点を考える」を再読する。
職業会計人は、プロフェッショナルであって商人ではない。
イトーヨーカドーやセブン-イレブンを中心とするイトーヨーカドー・グループの創始者から、経営の原点を学んでいる。
「王様が誰だかわからない時こそ、国がよく治まっている時だ」など至言が満載だ。
「お上意識を持たない」(125頁)でハッと息をのむ。
(引用開始)
お上意識を持った人は、・・・一人称ではなく三人称で発言します。
例えば、「私がやります」ではなくて、「社員はやるべきである」というようになるのです。
・・・しかし、三人称は商人の姿勢ではありません。
・・・「あの人」といった三人称的な冷ややかな姿勢・・・高飛車な姿勢は商いに禁物です。
(以上)
むむっ。。。
普段、頻繁ではないが、「あの人」を活用しているので、「ハッ」とする。
プロフェッショナルは、三人称で語ることが多い。
私は、プロフェッショナルであると同時に、商人だ。
以後、気をつけようと思う。(反省)
運命共同体そしてランチ
GW明けの月曜日、役員会議と幹部会議であった。
運命共同体である4役員、部長1人、次長2人、課長3人、係長1人の計11人で午前中、問題解決と成功への提案を行う。
太陽、空気、土がそれぞれの役割を自然界で果たすように、各人、組織が継続するように、自身のするべきことを完全に理解している。
運命を天に任せず、自ら拓くことを再確認した後は、幹部全員でランチを食す。
11人分のランチは、事前の回覧で何を食べるかによって、席順がアットランダム。
近くに座った幹部と束の間談笑することは意義がある。
頭脳をフルに酷使している会社内では、雑談は許されない。
こういうリラックスしたときに、成長した子供の話などして、運命を共にするプロフェッショナルの生活を聞く。
ランチの後は、電子申告を数件こなし、金沢税務署で打ち合わせ。
その後、社長就任挨拶のため、輪島へ向う。
能登有料道路を完全制覇した先に、目的地がある。
のんびりした風景が拡がるなか、ようやく到着し、代表者と後継者の方とご挨拶、さらに異業種交流会STLOWSのご案内もさせて頂く。
帰りの車中、マーケティングにつき暫し考える。
JCやロータリーなど各種団体で同じ会員に毎回会ったとしても、交友関係は限定的。
会社名をより知っていただくにはどうすれば良いか。
小冊子や書籍が効果的と再び断定づける。。。
仕事を人につける
多くの会計事務所は、人に仕事をつけている。
結果的に、その人がいないと困る状態となる。
そして、お客様も取引先も、その状態が困る。
以前、船井財産コンサルタンツ研修で、ホッピィビバレッジの石渡美奈氏の講演を聴いた。
「社長が変われば会社は変わる! ホッピー三代目、跡取り娘の体当たり経営改革」の著書の中で、仕事を人につける意味につき、こうご教授頂いた。
(引用開始)
わが社のように小さな会社では、余剰人員を雇用することなど到底できない。けれど命ある人間だから何が起こるかわからない。
「もしかして、朝、出社したら誰も来ないという有事がないとも限らない。その時に備えてどうしておけば良いのだろう。」
実は、小山さんに出会う前の私は、いつも心の中でこの不安を抱えていた。
「人に仕事をつけてはいけない。仕事に人をつける」
この教えを聞いたとき、私に走った衝撃を今でもよく覚えている。
「これだ・・・!」
しかし、創業以来90年以上、人に仕事がつくこと、部門を聖域化することが当たり前の文化になっていたわが社で、いきなり「仕事に人をつけよう」と話しても、当然のことながら理解されるはずもなく、こと製造部門の人手不足問題では、しばし、加藤木や製造部門の幹部と言い争っていた。
そんな彼らが、「人に仕事をつけていたら人員は幾らいても足りない。仕事に人をつける仕組みに変えていかなければ会社は利益を出せない」と気づいてくれたのは環境整備がきっかけだった。
(引用以上)
集団退職を経験している経営者や幹部の方ならば、「人に仕事をつける」状態の怖さを実感しているはずだ。
「君がいなければ、困る。だから、辞めないでくれ!」と懇願し、そして拒絶される。
あぁ、生々しくなったのでここらへんでやめておこう。
石渡氏が指摘しているとおり、部門を聖域化しているわけで、これは文化だ。
自分にしかできない仕事を日々量産していく。
自分しか知らない情報を机にしまいこんでいく。
この状況を打破することを「改革」という。
改革は概して遅々として進まない。
なぜか。
人に仕事をつけている場合、部下の進捗管理だけ判断の拠り所とし、現場に仕事をまかせきることができる。
そして、何かあれば部下を叱ればよい。
経営者や幹部は考える必要がないので、本音は現状維持で良い。
率直に言おう。これは強烈な自己否定だ。
「人に仕事をつける」やり方を否定するのは、私が相当ツライ。
(ツライから、役職がある)
二人担当性、ノウハウの文書化、データベース構築など考えるべきことが山積みとなるからだ。
スタッフの雇用、会社の存続を考えれば、当然ながら、お客様、ノウハウはすべて会社に帰属する。
第二四半期の中間にあたり、早くも来年の事業目標を意識し始めた。。。
坂田氏の理論で
久方ぶりのゴルフへ行こう。
場所は、能登カントリー倶楽部。

昨日、ゴルフ練習場で「バックスイングの時、右脇が空いているのが気になる。
締めたらどうですか?」と隣の方から教えて頂く。
私は、穏やかに初老の紳士に謹んでご返答する。
「坂田氏のジャイロスイング理論で学んでおります」と。
その白髪のジェントルマンが感嘆の声をあげる。
「ほぉ、恐れ入りました。坂田塾の生徒さんでしたか。」
それほど、本格的ではありませぬ(恥ずかしい)。
追伸
結果99(49・50)。
可もなく不可もなく。。。
あの日にドライブ
荻原浩著「あの日にドライブ」を読む。
銀行をリストラされた43才のタクシードライバーが主人公。
人生のやり直しがテーマの本著を読み、「ご縁」につき暫し考えてみる。
人生の岐路はすべて出逢いだ。
さて、自宅の郵便受けにAir Mailが届いている。
差出人は、20代の頃お世話になった会計事務所の先生からであった。
パシフィックビーナスの船上からの葉書。
世界一周の旅に出ているようで、イスタンブールが眼前にあると書かれていた。
2009年世界一周クルーズ(4月1日~7月12日、101泊102日)。
その葉書に鼻を近づけて息を吸い込めば、潮の香りがするような、そんな非日常的な感覚となる。

世界一周ブログ。
税制会計研究会
MMPG税制会計研究会に参加するため、東京へ向かう。
小松空港のラウンジで偶然、木村所長と会い、税務の打ち合わせを行う。
同じ飛行機に乗ることになっていたのか!(笑)
先ほどまで、携帯メールでやりとしていたのだが(苦笑)
羽田空港までは約50分のフライト。
機中、東野圭吾の「天使の耳」を読む。
交通事故など「車」に関する推理短編を集めた小説だ。
読みながら、マナー良くかつ安全運転を継続しようと再認識できた。
車は便利だが、怖いもんだ。
MMPG本部に11時過ぎに到着すると、A専務理事とK会長の打ち合わせがすでに始まっていた。
私は、陪席という形で、お話だけ拝聴させていただく。
昼食後、W研究員、H副会長が到着し、いよいよ税制会計研究会がスタートする。
まずは、税制に関係する先生方の質問を我々研究員が文書で答える方針を確認する。
責任の所在を明確にするため、若干の謝礼もいただけるようだ。
次に、資格認定試験のレジェメ改定と試験問題に話が及び、今年度の研修テーマの選定につき議論する。
発表は公の場ですることとしよう。
懇親会は、土佐料理の「ねぼけ」。
K会長、W研究員、H事務局員と4人で語らい、気づけば日付を超える1時間前。
新たなステージに心躍る1日であった。
杏っ子
室生犀星の「杏っ子」を読む。
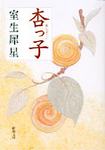
犀星の自伝と言われている小説。
この小説は、私生児として生まれ、生後まもなく養子に出された平山平四郎という作家の人生を描いている。
犀星は、恵まれぬ幼少時代を描きながら、産みの母親を求め続けている。
「ただ、このような物語を書いているあいだだけ、お会いすることが出来ていた。(中略)物語をつづるということで、生ける母親に会うことのできるのは、これは有難いことのなかの特に光った有難さなのである」。(24頁、引用)
かの有名な詩「小景異情」のなかで、ふるさとは遠きにありて思ふものと詠んだ故郷金沢に対する複雑な思いを少しだけ理解できた気がした。
[小景異情 その二]
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
山中温泉へ
GW中何処も行かないのも何なので、近くの山中温泉に宿泊することとする。
散歩に適した川沿いや橋を数時間かけて歩く。
途中、足湯につかり、疲れを癒す。
歩いていても温泉につかりながらも考えることは会社のことばかり。
マーケティングとして会社の出版物が必要と思う。
専門特化の結果として、一番本が適切であろう。
皆様に会社の業務を知って頂く機会をつくろう。