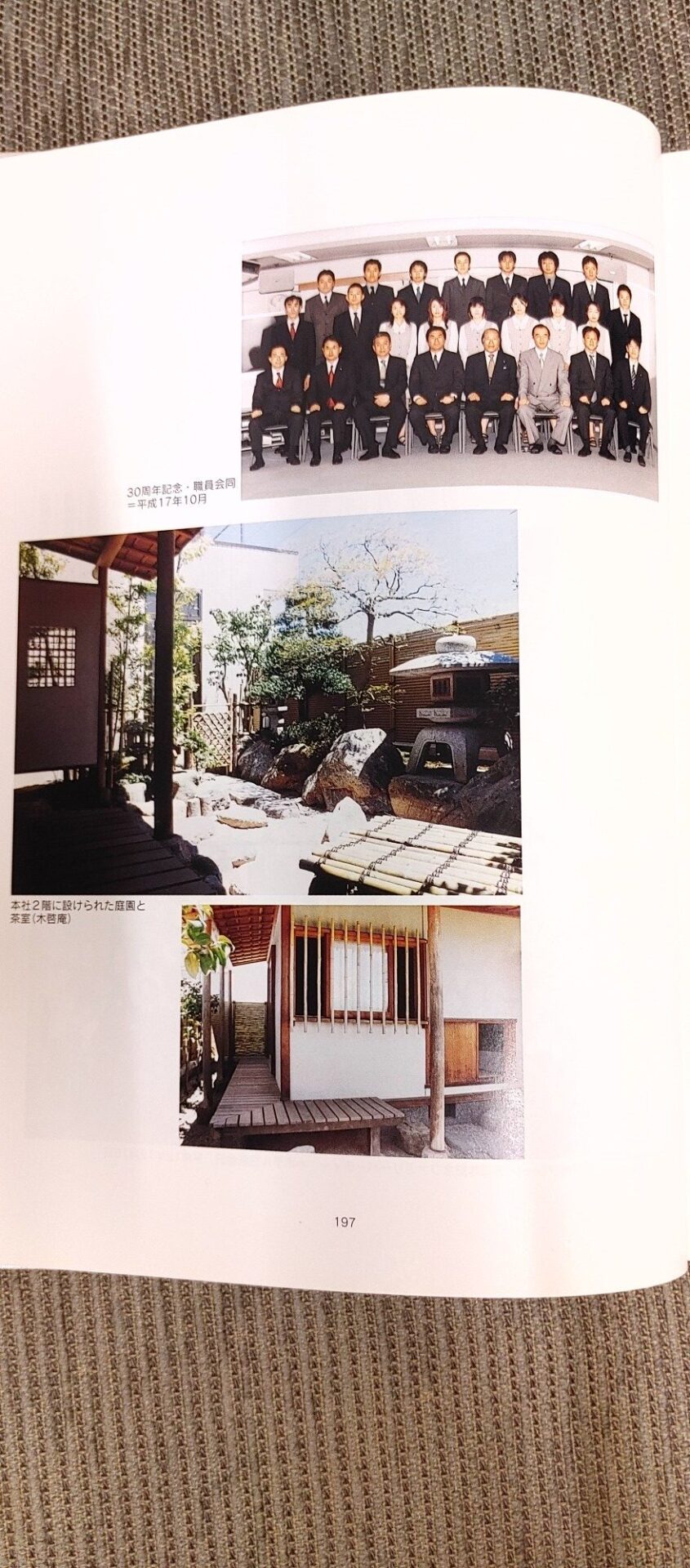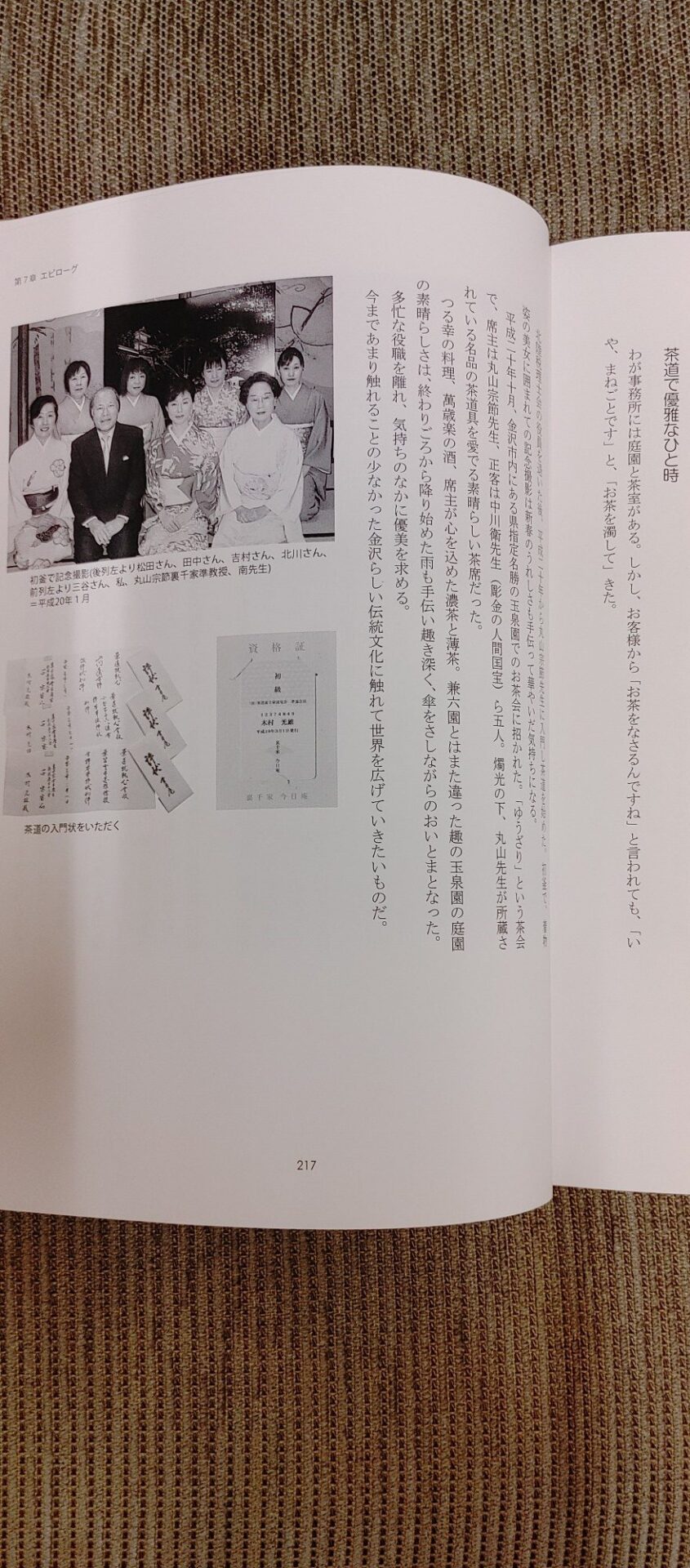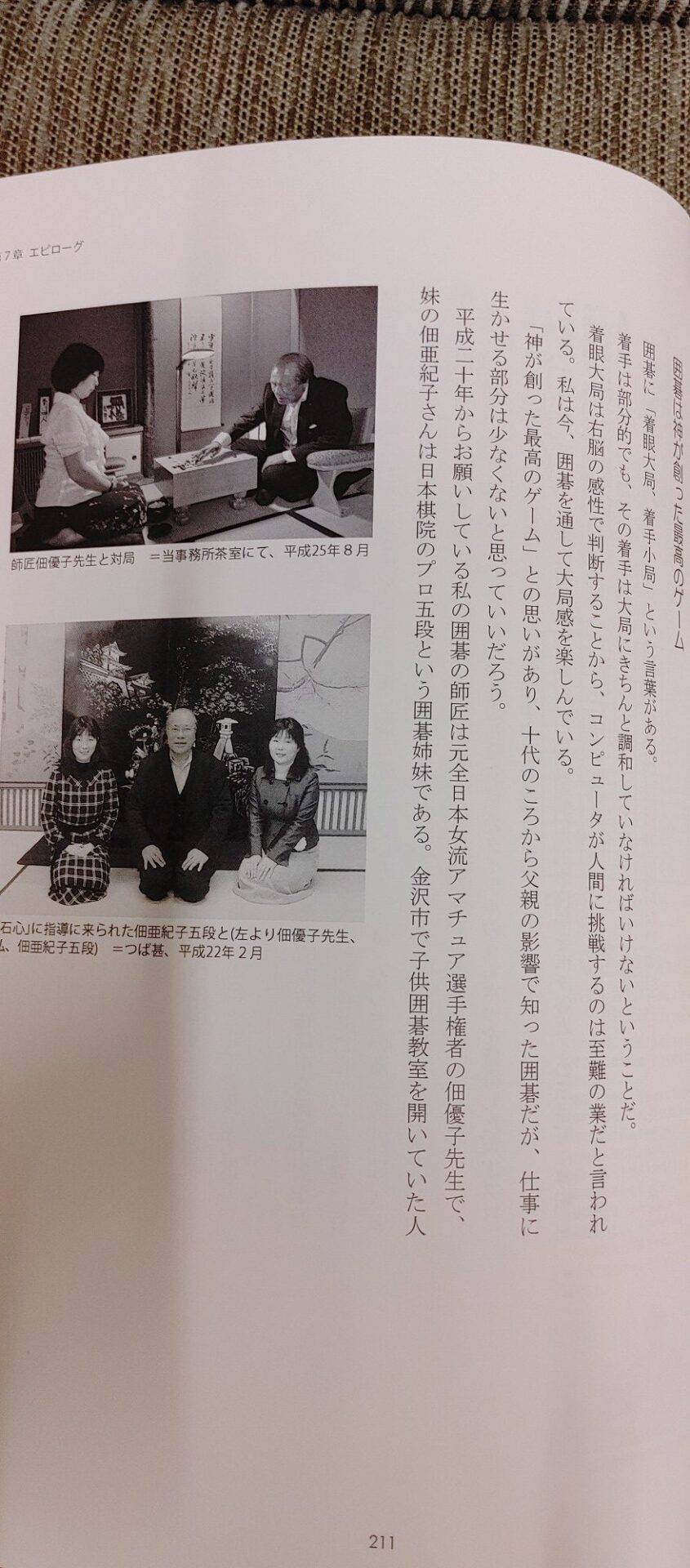6月30日、北陸税理士会金沢支部長を拝命致しました。
新支部長挨拶として、以下のことを述べました。
1.支部長就任にあたって
このたびの総会にて、金沢支部長に就任させていただくことになりました木村岳二でございます。歴史と伝統ある金沢支部の支部長職を担うにあたりまして、今まで受けた恩を心に刻み、誠心誠意全力で尽くします。皆様のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2.事業計画の推進
先ほど総会審議にて川上議長の円滑な議事進行のおかげもあり、事業計画のご承認を賜りました。税理士会員が地域社会の発展に貢献する事業計画です。 昨年の税理士法改正により、税理士業務のデジタル化元年を迎えました。税理士法改正はされたものの、デジタル化に対応に苦慮している会員も少なからずいるのも事実です。
ただ、税理士会は強制加入の性格上、デジタル化は全員で取り組む必要があります。アフリカのことわざに「早く行きたいなら一人で行け。遠くへ行きたいなら全員で行け」という言葉があります。400名の会員にあまねく情報を伝え、全員で努力することにより、より遠くへそして税理士制度の維持発展という高みに行けるものと考えております。
物価高そしてコロナ禍前と比して活動も活発化し、事業費が増加しております。支部会費の値上げも検討する時期が来るかもしれません。この場合も早く決めるのではなく、可能な限り支部会員の意見を徴し、決議をしたいと考えております。会員による会員のための会務を行います。
3.税理士制度の更なる発展のため
今日の税理士制度の発展は、税理士による納税者の信頼に応えた実務対応とこれまで築かれてきた税務当局との信頼関係によるものであり、会務の一層の活性化を図ることで税務当局並びに関係諸団体との絆をこれまで以上に強固なものにして、税理士制度の更なる発展につなげてまいります。
4.結び
結びになりますが、今後とも金沢支部の至宝であるブロック連絡員会議で会員の意見に傾聴し、協同組合及び政治連盟とも連携し、会員の懲戒や会費未納がないことを祈りつつ、本日ご臨席の皆様方には金沢支部に対しましてご支援を重ねてお願いいたしますとともに、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、支部長就任の挨拶とさせていただきます。