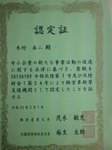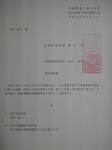第31回定時株主総会の模様です。
お客様の模範会社となるため、開催しております。
決算書内容、剰余金処分、取締役選任等、株主の方々より承認をいただきました。
(平成25年2月23日 弊社3階会議室にて)
金沢会計人 のすべての投稿
経営革新等支援機関の認定登録のお知らせ
経営革新等支援機関の認定登録のお知らせ
平成25年2月1日付けで、経営革新等支援機関として認定を受けました。
認定証が届きましたので、ご報告申し上げます。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、貴殿を。。。経営革新等支援機関として認定することを証する」
経済産業大臣 茂木 敏充氏
内閣府特命担当大臣 麻生 太郎氏
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
「路上から武道館へ」
「路上から武道館へ」宮崎菜穂子
2013年の始まり、この歌を聴きました。
「路上から武道館へ」 /宮崎奈穂子
この歌を拝聴し、この言葉を想い出しました。
「過去相も現在相も決定相ではない。あくまでも過程の一場面に過ぎないのだから、君がこれから自分の人生を良くするか、もっと悪くするかは、君次第だ」
イエローハットの創業者、鍵山氏の恩師の言葉。
楽は苦の種、苦は楽の種。
楽と苦は背中合わせであり、楽には苦が、苦には楽がついて回る。
宮崎さんの歌から、こんなことを学びました。
事業を通じて夢を実現する皆様に聴いて頂きたいです。
「今は自分だけの夢じゃない ♪
路上から武道館へ ♪」
英語で感動することを「Touch」(触れる)という。
人の心に触れた時、人は動きだす。
人を幸せにする会社
(大きな独り言~大殺界からワクワクへ)
先日、ある方から六星占術を教えて頂きました。
占いとは縁遠く興味もありません。しかし、なんとなく調べてみると、2013年が「大殺界」の入り口に。(笑)
誰もが12年毎に経験するようでして、私の場合、12年前や24年前を振り返ると、確かに、大変な年でした。
2001年(平成13年)の入社時、1989年(平成元年)の大学入試など。
大変とは、「大きく変わる」と書きます。
事実、その当時の大変な経験で、自分自身が大きくブレイクスルー(変革)できました。
そういう意味では、節目の年となると思い、ワクワクしております。
どんな状況であれ、愚直に良い習慣を実行し、謙虚に学習して参ります。
さて、本文です。
『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズ著者、坂本光司最新刊の紹介です。坂本氏は、「経営の目的は人を幸せにすること。」と喝破しています。

「人を幸せにする会社」は、某金融機関若手経営者の会のテキスト候補でもあります。
(目に見えない財産こそ大事)
会計事務所は、数多くの財務諸表を作成するお手伝いをしています。そして、財務諸表は、課税庁や銀行などに対し、それぞれの目的で活用されています。
決算書は円単位の表示しかなく、すべての事象を記載できるわけではありません。
今、目に見えない資産こそ、大事な時代となりました。
高業績をあげる中小企業に共通項があり、3つの力があることがわかります。
「経営理念力」・・・正しい経営理念を浸透させる力
「人財育成力」・・・社員のやる気を高める
「信頼形成力」・・・社員同士、社員の家族、取引先や地域社会などとの絆を結ぶ
いずれも、財務諸表にも記載できない。目に見えない3つの企業資源”を育むことで、「共感力」をつくりだしている。
「人を幸せにする会社」として、「四国管財」 が挙げられています。
経営理念の力で“憧れて入社したくなる清掃会社”に生まれ変わったビルメンテナンス企業。
両親や子どもから誇りを持てる会社にしたいという強烈な願いから、その意思を貫きました。感動しましたので、伝えるべく、某金融機関若手経営者の会の教材にしようと思います。
(投信のイメージ変革元年)
先日、ご縁を頂きまして、投資会社「鎌倉投信」の話を聞く機会がありました。
投信の響き。
何を連想するかといえば、「損」「危ない」とネガティブな感じでしょう。
そんな投信のイメージを吹き飛ばす会社が、「鎌倉投信」です。
鎌倉投信の投資基準は、「人を幸せにする会社」かどうか。
21世紀は社会の課題を解決する企業が存続できます。
個人的に、この投資基準は正しいと思います。
新年会での出会い
ある銀行の新年会で、以前にご縁を頂いた番組の司会担当、金子アナウンサー(右)、北陸朝日放送代表取締役専務の岡﨑裕平氏(左)と歓談。
その番組とは、2006年1月放送、HAB(北陸朝日放送)「健康の館」。
http://www.hab.co.jp/yakata/200601/200601-4.html
当時の肩書は専務取締役で、35歳。
「かかりつけ医の役割とIT活用」についてのインタビューを受けました。
「健康の館」は惜しまれつつも2007年2月で終了。。。
http://www.hab.co.jp/yakata/index.html
2013年きんどん会 新年会
STLOWS新年会2013
会計事務所の経営支援
北陸三県の黒字割合について
金沢国税局の法人税の課税状況(平成22年度)を見ると、黒字企業の割合は、以下のとおりになっております。
・富山県 28.7%
・福井県 27.2%
・石川県 24%
全国の黒字法人の平均が3割弱です。
北陸においても、一部の黒字法人が法人税を納付している状況です。
税金の計算よりも、赤字企業をなんとかしなければならない。
最近、税理士も経営支援の担い手として社会から期待されるようになりました。
会計事務所の経営支援のあり方について、あるコラムを書きました。
【コラム】「社長の『会計力』をアップさせる簡単な質問」
最近、中小企業のお客様と某銀行へ同行し、社長の会計力の重要性に改めて気づきました。
社長自身が完全に決算書を理解していない場合、利益の源泉や資金繰りのことなど自信をもって、銀行の支店長の問いに答えられないのです。
決算書は社長の成績表です。社長自身が決算書を完全に読みこなし、利害関係者に説明できるようにしなければならないと痛感しております。
毎月、会計事務所はお客様に出向き、月次決算書の説明をしています。私の場合、会計力を上げるため、「今月の現預金残高はいくらですか?」「期首や前月からいくら現預金が増えていますか?」と社長に質問するようにしています。
先ずは、現預金の増減原因を記述しているキャッシュフロー計算書で現預金残高を毎月確認する。そして、現預金増減の原因を分析することが大事だと思います。企業は、赤字では倒産しません。資金繰りに詰まったとき、倒産します。
社長の会計力をアップさせるため、現預金が期首ないし前月よりも増えているか否か確認することから始めてはいかがでしょうか。
末筆ながら、皆様の社業が益々発展しますように、心から祈念しております。