現在、私は、MMPG(メディカルマネジメントプランニンググループ)の税制会計研究会に属しており、研究委員をしております。
MMPGは、医業・福祉・介護事業を研究している会計事務所の集団です。
この度、MMPG編集で、税務研究会出版局 (2011/10)より、「医療・介護・福祉の消費税」が出版されたので、報告いたします。
(狙い)
医療・介護・福祉事業を行う医療法人等の経理担当者、顧問税理士、会計士、医業経営コンサルタントの方などのプロフェッショナル向けの消費税に関する辞書。
これを見れば、消費税に関することは解決。
(POINT)
・医療・介護・福祉などの収益の大半は消費税法上非課税とされています。
・ケースによっては課税されるものもあり注意を要します。
・医療・介護・福祉事業の消費税の課否判定を中心に、課税事業者となるのか、簡易課税は選択できるのか、控除対象外消費税等の処理はどのようになるのかといった点について137のQ&Aでわかりやすく解説しています。
「医療・介護・福祉の消費税」
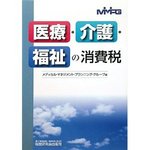
金沢会計人 のすべての投稿
経営の教科書とメモの重要性
「嫌な思いというのは、自己中心主義の度合いに比例する。」
(新将命著 経営の教科書―社長が押さえておくべき30の基礎科目 81頁)

この一文を目にし、新氏は本物だと「経営の教科書」を読み進めました。
私は、男女問わず、信念を持つ熱い人が好きです。
そういう意味で、情熱度は非常に大事な指標と考えています。
新氏は、その著書の51頁で、「会社の情熱度を測る三つの方法」をこう語っています。
①講演会や勉強会で前の席から埋まること。
②講演会や勉強会を聞きながら、メモを取る人が多いこと。
③笑いが出ること。何を言ってもシラッとして笑いが出ない会社は、心身両方或いはどっちかの「疲れ」か、目の前の仕事に必死でやっているが、会社の将来や方向性については何も知らされておらず、お先真っ暗であるという場合が多い。
他には「何か質問は?」といわれて、どんどん手が上がること。
メモをとることの重要性については、折を見て説いてまいりましたが、先日のある研修会で強烈に痛感しました。
新人だと思われる方が一番前に座って、メモをとるどころか腕を組んで聴いていました。
久方ぶりに唖然としたわけです。
オイオイと突っ込みを入れる前に、ハタと当社はどうかと振り返りました。
この3点を徹底し事業計画書に反映したいと考えています。
「社長ブログ 宝在心」
ブログ名を「職業会計人の激白ブログ」から「社長ブログ 宝在心」と変えさせて頂きました。
「宝在心」は、上杉謙信公の言葉です。
文字どおり、本当の宝は、外ではなく、内なる心にあると思います。
上杉謙信公家訓16カ条を羅列します。
1.心に物なき時は心広く体 泰(やすらか)なり
(物欲がなければ、心はゆったりとし、体はさわやかである)
2.心に我儘なき時は愛敬失わず
(気ままな振舞いがなければ、愛嬌を失わない)
3.心に欲なき時は義理を行う
(無欲であれば、正しい行い、良識な判断ができる)
4.心に私なき時は疑うことなし
(私心がなければ他人を疑うことがない)
5.心に驕りなき時は人を教う
(驕り高ぶる心がなければ、はじめて人を諭し教えられる)
6.心に誤りなき時は人を畏れず
(心にやましい事がなければ、人を畏れない)
7.心に邪見なき時は人を育つる
(間違った見方がなければ、人が従ってくる)
8.心に貪りなき時は人に諂(へつら)うことなし
(貪欲な気持ちがなければ、おべっかを使う必要がない)
9.心に怒りなき時は言葉和らかなり
(おだやかな心である時は、言葉遣いもやわらかである)
10.心に堪忍ある時は事を調う
(忍耐すれば何事も成就する)
11.心に曇りなき時は心静かなり
(心がすがすがしい時は、人に対しても穏やかである)
12.心に勇みある時は悔やむことなし
(勇気を持っておこなえば、悔やむことはない)
13.心賤しからざる時は願い好まず
(心が豊かであれば、無理な願い事をしない)
14.心に孝行ある時は忠節厚し
(孝行の心があれば忠節心が深い)
15.心に自慢なき時は人の善を知り
(うぬぼれない時は、人の長所や良さがわかる)
16.心に迷いなき時は人を咎めず
(しっかりした信念があれば、人を咎めだてしない)
職場と「負ける練習」
職場と「負ける練習」
弊社の基本理念は、昭和53年に制定しております。
「職場を自己修練、自己実現の場と心得・・・とあります。」
相田みつお先生の「負ける練習」を拝読し、職場は、日々の練習の場だと再認識しました。
「負ける練習」
柔道の基本は受け身
受け身とは投げ飛ばされる練習
人の前でたたきつけられる練習
人の前でころぶ練習
人の前で負ける練習です
つまり、人の前で失敗をしたり恥をさらす練習です
自分のかっこ悪さを多くの人の前でぶざまにさらけ出す練習
それが受け身です
長い人生にはかっこよく勝つことよりも
ぶざまに負けたりだらしなく恥を
さらすことのほうがはるかに多いからです
そして負け方や受け身のほんとうに身に付いた人間が
人の世の悲しみや苦しみに耐えてひと(他人)の胸の痛みを
心の底から理解できるやさしく暖かい人間になれるんです
そういう悲しみに耐えた暖かい心の人間のことを
観音さま、仏さま、と呼ぶんです
相田 みつを (著) 「一生感動 一生青春」 76頁引用
パラダイムシフトと合同会社設立
パラダイムシフトと合同会社設立
○所有から共有へ
未来の歴史家が、我々が生きている現在を、どんな時代というか空想してみます。
インターネットがほぼ網羅され、フェイスブックのようなソーシャルネットワークも完備されつつある状況を歴史家がどういう時代と判断するか。。。
21世紀の社会と経済は、ネットコミュニティの時代であり、「所有」から「共有」へとパラダイムシフトした元年と言えるのではないでしょうか。
○資本提携の世界から使命感のつながりの世界へ。
私見ながら、組織再編の世界においても、「所有」から「共有」への潮流があると思います。
資本を投下して子会社化するという時代から、使命感や大義といった資本とは関係のない提携の時代へと移行していくものと考えております。
なお、後継者がいない場合の第三者承継(M&A)は、時代を超越して有益です。
そこで、大義を同じくする会計事務所と提携して、合同会社を設立しました。
第一弾の企画は、資産家防衛戦略です。
「今、求められる統合的資産管理」セミナー開催決定
内容
1.世界一資産管理・資産移転が難しい国ニッポン
2.求められる全体最適戦略
3.簡易設計・資産管理のプラットフォームのご紹介
4.エンディングノートのご紹介
5.プロの総合資産コンサルティング
6.個別無料相談会
セミナー開催日
•大阪 10/24(月)14:00~16:30 ヒルトン大阪
•東京 10/28(金)14:00~16:30 東京プリンスホテル
•京都 10/31(月)14:00~16:30 ホテルグランヴィア京都
•金沢 11/14(月)14:00~16:30 ホテル日航金沢
http://www.shk-shisankanri.com/company/index.html#seminar
事業承継と経営理念の見直し
私は、事業承継の際、後継者に経営理念を見直しを提案しております。
経営理念とは、事業発展するため、社長の思いや使命を社内外に発表したものです。
経営理念が「会社が何のために存在しているのか」につき、誰にでも理解できるものになっているかどうかチェックが必要です。
⇒経営理念見直しのポイント
1.経営者の目的や目指す方向がはっきりしているか?
2.経営者の哲学、人生観、社会観、経営観、すなわちバックボーンがあるか
3.社長本人だけでなく、社員、お客様にも共感を得られるか?
4人間性や社会の本質に即したものか。時代を超えて超越できるか?
5.国内はもとより海外で通用するか
6.全社員が日常生活でも心の拠り所とできるか
7.理念を実践するなかで人が育つ方向になっているか
8.絵にかいたモチではなく、常に活かすことができ、また実践できるものか
9.企業が存続できる顧客創造、社会奉仕の要が入っているか
10.それらの結果、社会から報酬を得られ収益向上につながるかどうか
東川鷹年先生の「社員がワクワクして仕事をする仕組み」日本経営合理化協会出版局
203~207頁「経営理念を原点から見直す」参照。
第二回提案力コンテスト
今年も、組織の継続学習の集大成として、提案力コンテストを実施し、プロフェッショナルスタッフが発表し、全員で聴き、優秀者を表彰させて頂きました。
ドラッカー氏によれば、事業発展には、継続学習と教える組織が必要と説いております。
全員の経験や知識を共有するべく、教えていただく機会を全員に設けております。
継続学習が一つの弊社の特徴かと改めて思います。
2011.9.9 第2回 ㈱木村経営ブレーン 提案力コンテスト IN 七尾サンライフプラザ(七尾市)
≪発表内容≫
1.ホテル事業の再生計画
2.賢いお金の貯め方
3.相続のしくみと資産承継対策
4.e.c.o. ~えっ、こんなに、お安いの?~
5.意外とやれるぞ!情管 ~確定申告編~
6.少人数私募債の提案
7.親子承継は人間関係で結果が変わる2つの事例について
8.Happy 事業承継~幸せになりたい人が今からやるべき事~
9.組織再編業務事例 合併・分割業務ってなんや?
10.あなたを一流のプロにするR/Nの使い方~コンサルティング商品戦略
11.在宅療養支援診療所の医療法人設立認可申請提案事例について
12.WebPRのすゝめ
13.○○クリニック 患者満足度アンケートについて
14.ソーシャルメディアコンサルティング~Webコミュニケーションの感動を伝える~
≪審査手順≫
・審査員 審査権は役員・社員・契約社員 合計34名
・審査基準
内容(実現性・正確性・生産性・新規性・企画性) 40点
発表(表現力・資料) 30点
全体(総合力) 30点 計100点
≪入賞テーマ≫
優勝:ソーシャルメディアコンサルティング~Webコミュニケーションの感動を伝える~
二位:あなたを一流のプロにするR/N(ランクアップノート)の使い方~コンサルティング商品戦略
三位:WebPRのすゝめ
特別賞:在宅療養支援診療所の医療法人設立認可申請提案事例について
上位入賞テーマには、FacebookのようなWEBを活用した事例がありました。
事業承継コーディネーターの新聞記事
今年の4月より、中小機構北陸支部の事業承継コーディネーターを拝命いただいております。
その活動の一環で、新聞記事に掲載された記事(事業承継セミナー)がありますので、掲載いたします。
23年9月事業承継セミナー.pdf
建設工業新聞 平成23年9月9日(金) 朝刊より抜粋。
日本政策金融公庫金沢支店国民生活事業、中小企業基盤整備機構北陸支部は8日、金沢市広岡3
丁目の同支部会議室において事業承継セミナーを開催した。
この中で中小機構事業承継コーディネーターの本村岳二氏が「経営計画書の作成は先代との価値観を合わす作業」と定義づけ、「計画書を先代が添削することにより、経営や後継者のへ思いを共有できる」と指摘した。
株式会社木村経営ブレーンの代表取締役である同氏は、朝のあいさつの際、社員との会話を心がけているとし、「うちの会社に来て、働いてくれてありがとう。感謝していますという思いを込めてあいさつしている」と述べ、リーダーにはスキル以外に社員を思いやる気持ちも必要と訴えた。同セミナーには、中小企業の経営者や後継者ら15人が参加した。
資産防衛対策~韓国編
資産防衛対策~韓国編
1.円は本当に強いのか?
1ウォン=14円(2011年8月28日現在、1ドル=77円)と円高ウォン安の状態が続いております。日本の輸入業者にとっては、有難い状態ではありますが、いつまでこの状態が続くかはわかりません。
今の円高状態は、日本の経済のファンダメンタルズを反映しているのか、通貨の不美人競争の結果、ドルとユーロとの比較優位で円が強いとなれば、いつ円安になっても不思議ではありません。
この状況下、円安に備えて外貨で貯金する人が増加しております。
資産防衛の一つの例として、韓国で実際に輸入しているA氏に協力を頂き、実際、ソウルの市中の銀行で、ウォン建ての定期預金を1年間預ける現場を見学させて頂いた。
2.市中での換金
銀行では換金レートが不利なため、市中の換金所で75万円をウォンに変えました。
8月30日のレート1円=13.9ウォンなので、10,425,000ウォンに換え、いざ銀行へ。

(写真は、10,000,000ウォン)
3.銀行での手続き
先ず、通帳とキャッシングカードの作成するには、パスポートの提示が必要となります。
また、インターネットでいつでも残高閲覧も可能だそうです。

1年定期の場合
○1千万円ウォン 3.8%(但し、2年以上預けた場合、3.9%となる。)
○3千万円ウォン 3.9%
○1億ウォン 4%
10,000,000ウォンを預けた場合、1年後の2012年8月30日時点での利息は、380,000ウォンとなります。
お客様満足と社員満足は会社という車の両輪
お客様満足と社員満足は会社という車の両輪
多くの会社は、お客様第一としています。
坂本光司著「日本でいちばん大切にしたい会社」によれば、素晴らしい会社は、社員とその家族を幸せにすることを第一の使命としています。
なぜでしょうか?
お客様を感動させるようなサービスを提供しなければならない社員が、自分の会社に不平・不満を持っているならば、お客様に身体から湧き出るような感動を与えるようなサービスはできないと思います。
所属する組織に対して満足度が高く、帰属意識の高い社員でなければ、お客様が満足するサービスはできません。
うわべだけのニコニコ顔は、目の肥えたお客様には通用しないと思います。

