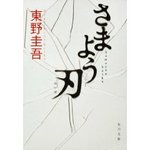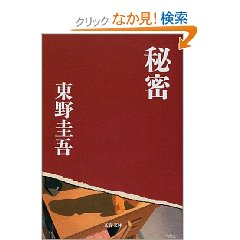東野圭吾著「さまよう刃」 (角川文庫) を完読。
遺族の復讐と少年犯罪をテーマにした本著の読後感はとても重い。
現在の法治国家は、昔の敵討(かたきうち)を許さない。
では、誰が仇討ちを果たすのか。
答えは見つからない。
さて、某国のミサイル問題。
歴史を振り返るに、独裁者の末路は既に決まっている。
セルビアのミロシェビッチ、ルーマニアのチャウシェスクのごとく。
テーマ、重いなこりゃ。。。
眉間に皺がよってしまう(笑)
来週の幹部会議資料をまとめて、気持ちを落ち着けよう。
金沢会計人 のすべての投稿
確定申告体制につき討議
今回のMMPG義継会は、名南経営センターさまにて開催される。
今回は、主に確定申告体制につき討議する。
最初、所内の検閲体制を各事務所が発表した後、税務署退官者で構成される審理室ないしは退官者との顧問契約は必要か否かなど意見交換させていただく。
そして、議論のメインは、電子申告に移る。
先日の税務調査でも、税務調査官が電子申告のご苦労を吐露したものであった。
送信されたデータと、郵送される源泉徴収票や医療費控除資料などの付属資料の突合が煩雑だと。
従前の紙申告の場合、その突合にはさほど時間がかからなかった。
現在は、完全電子申告とはいえず、過渡期。
付属資料のペーパレス化により、電子申告時代の到来と言える。
他にも、事務所体制につき、ご教授いただく。
「のれん」について
M&Aに携わっていて、経営者の皆様が「のれん」の会計、税務処理につき、本質的なところをご理解されていないと感ずる。
M&Aする場合、買収法人がオーナーである個人株主から被買収会社の株式を取得するケースがほとんど。
買収法人は、その会社を100%子会社とするわけです。
株式の取得価額が純資産価額を上回る額が営業権ということになります。
例えば、株式の取得価額が100、純資産価額が60とするとその差額の40が営業権です。
その営業権を株式取得の場合、どう会計・税務上、認識するか?
子会社を株式取得する場合、営業権の処理について、特に会計処理は必要ありません。
単体での処理(会計上)
(M&A時の仕訳)
(借方)子会社株式 100 (貸方)現金 100
株式取得(株主移動)のため、税務上も営業権の計上は認められません。
ただし、営業権は、組織再編の一形態である営業譲渡や非適格合併の場合には発生します。
「のれん」認識は、組織再編の形態により異なるわけです。
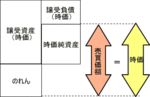
(杉野会計事務所HPより転載)
苦難にある者たちの告白
2月に、役職が変わってから、私にとっては、難しい問題が続出している。
そう、試されているかごとく。
この試練をどう立ち向かうか。
今日、キーマンネットワークの中島氏もこの詩をアップしていましたが、私も、自分自身を励ますため、この詩をブログに記載しよう。
ニューヨーク大学のリハビリテーション病院の壁にあるという「苦難にある者たちの告白」。
日本語、英語ともに含蓄のある力強い言葉です。
「苦難にある者たちの告白」
-ある患者の詩-
「大きなことを成し遂げるために 力を与えてほしいと神に求めたのに 謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。
より偉大なことができるようにと健康を求めたのに より良きことができるようにと病弱な体を与えられた。
幸せになろうとして富を求めたのに 賢明であるようにと貧困を授かった。
世の人々の称讃を得ようとして権力を求めたのに 得意にならないようにと失敗を授かった。
求めたものはひとつとして与えられなかったが 願いはすべて聞き届けられていた。
言葉に表されていない祈りが叶えられていたのだ。
ああ、私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。」
「A CREED FOR THOSE WHO HAVE SUFFERED」
「 I asked God for strength, that I might achieve
I was made weak, that I might learn humbly to obey…
I asked for health, that I might do greater things
I was given infirmity, that I might do better things…
I asked for riches, that I might be happy
I was given poverty, that I might be wise…
I asked for power, that I might have the praise of men
I was given weakness, that I might feel the need of God…
I asked for all things, that I might enjoy life
I was given life, that I might enjoy all things…
I got nothing that I asked for — but everything I had hoped for
Almost despite myself, my unspoken prayers were answered.
I am among all men, most richly blessed! 」
緻密さ
気がつけば、はや4月。
年々、月日が経つのが早く感じられます。
当ブログも、3年近く更新し続けています。
カタツムリがゆっくり這うように、その軌跡が残っている。
簡単な気持ちで始めたのに、すっかり朝の習慣となってしまった。
さて、昨日は、確定申告フローを見直すなど、内部管理中心で過ごす。
攻守両面のバランスを意識し、私の苦手な緻密さを自己修練で身につけたい。
呼吸法の大事さ
最近、呼吸が大事と気付く。
息を吸うよりも、吐くほうが、エネルギーが格段にいる。
先日、息を吐くことを意識して、結果的に息を吸えば、内転筋も鍛えられるとご教授頂く。
内からの筋力アップだ。
日常、息を吸ってから、吐いている。
今後、意識してみたい。
五木 寛之,帯津 良一(著)「健康問答 本当のところはどうなのか? 本音で語る現代の『養生訓』」
五木寛之氏が、その著書の中でこう言っている。
以下、引用したい。
「息を吸うというのは、自然に吸ってしまうんだけれど、吐くというのは……。
このあいだ、お医者さんかどなたかの、数多くの人を看取ってきた方が書いた本を読みました。
その方によると、人が死ぬとき、息を引き取るというけれども、ほんとうに、スーッと息を吸って亡くなるんですってね。
ハーッと、吐きながら死ぬ人はいない。
吸った息を吐く力がなくなったとき、命は終わる。
逆に、赤ん坊が生まれたときは、お産婆さんがベシンと尻をたたくと、オギャーッと泣く。
あれは吐く息なんでと。
力のある人は息を吐けるし、息を吐く力がなくなって、スーッと臨終になるので、吐いて臨終する人はいない、と書いてありました。
だから、「息を引き取る」という。
吐き取るんじゃないんですね。
そう考えてみると、吸う息、吐く息とありますけれども、吐く息が、生きる命にとっていかに大切かということが、非常によくわかりますね。」
秘密
最近、東野圭吾氏の本をよく読む。
私のナンバー1は、「秘密」。
二番目以降は、「容疑者Xの献身」「宿命」「手紙」「時生」などなど続きます。
極論すれば、私の人生観を変えた本。
究極の仮定で、人生の本質を突く東野氏という天才の出現が、日本の小説を変化させる。
(内容)
妻・直子と小学5年生の娘・藻奈美を乗せたバスが崖から転落。
妻の葬儀の夜、意識を取り戻した娘の体に宿っていたのは、死んだはずの妻だった。
その日から杉田家の切なく奇妙な“秘密”の生活が始まった。
金融崩壊時の会計人の原点
先日、TKC北陸会報4月号の「巻頭言」を書かせて頂く。
そのドラフト(草案)を公開します。
(会計人の可能性)
TKCの創設者である飯塚毅先生は、「アメリカにおいて、保険代理業務は、職業会計人の正当義務であり、日本でも導入すべきだ」と提唱しました。そして、「企業防衛制度」の名の下に、大同生命との提携により、全国で3兆円の保険契約高達成を目指して企業防衛制度推進運動が開始されました。
木村光雄所長が企業防衛庁長官と呼称されるほどまでに、企業防衛推進に傾注していた頃、TKC全国会の企業防衛制度保有契約高16兆円という数字は、途方もなく遠大なものでありました。当時、人類が月に行く位、想像もつかぬ目標数値であったでしょう。しかしながら、昨年、ミッションという名に恥じない壮大なる職業会計人のロマンを見事に達成したのでした。
千里の道も一歩から、着実に職業会計人の職域拡大と共に数値も積み上がってきました。そして、会計事務所経営も私のような2代目経営者へとバトンが移るにつれ、その創業の精神も薄らいできたように感じます。先達者の業績を既与のもとして、我々は何も挑戦していないのではないか自問自答しております。
(会計人の新たなる挑戦)
理想のリーダーのやるべきこととは何でしょうか。僭越ながら、前任者達が育ててきた仕事・事業をベースにして、次の世代が果実を享受できるような新しい仕事の種を蒔き、土を耕しておき、企業の継続的発展を図るのがリーダーの仕事と考えております。
前任者達の育てた仕事の果実を徹底的に収穫することだけに集中し、それを自らの実績として誇り、次の世代への先行的投資努力を一切しないタイプのリーダーは最悪です。
三井物産元副社長の島田精一氏は、「焼畑略奪農業型リーダーになってはいけない」。そして、「リスクなきところに利益なし」と言っております。また、陶芸家の河井寛治郎氏は、「過去が咲いている今。未来の蕾で一杯な今。」とも語っております。
(金融崩壊時の会計人の原点)
「この秋は、雨か嵐か知らねども、今日も一日、田の草を刈る。」二ノ宮尊徳
(田植えをしてから、秋の刈り取りまでの、期間中に台風が来るかもしれない、どんな自然災害がくるだろうかと考えたら、眠れなくなるほど心配になることもあるが、それはそれとして、先ず今、出来ることをしっかりやる。)
アメリカの金融危機以降、その視点や距離感により、100年に1度の大恐慌との論調がある一方、千載一遇のチャンスの到来など両極端の見解が多いように感じます。この経営状況の中で、悩んでいる経営者も多いことと推察致します。
上記の二ノ宮尊徳の言葉どおり、我々会計人の拠り所は、公正無私の理念であり、行動は、脚下照顧を基本とすることは不変だろうと思います。農作も秋に台風が来るからといって、春に種まきしないことはありません。足下を見て、役割分担をし、それぞれ今日の務めを果たすことが大事なことと信じています。
切り替え力
組織再編をコアコンピタンスとする監査法人の研修旅行に同行させて頂く。
但し、滞在中のブログ記事は、事前にいくつか用意させていた内容を記載しますので、ご容赦ください。
さて、岡本 正善著「メンタルスイッチ―『切り替え力』が身につく実践トレーニング」を読む。
過去の失敗、将来への不安、単調な日々の惰性、プライベートと仕事の混同…。
無意識のうちに心に浮かぶ感情は、目の前の事に対する集中力を妨げ、また、簡単には振り切れずにさらなる悪循環を生んでしまう。
日常的に陥りがちなこの「メンタルの落とし穴」から抜け出すための実践トレーニングとケーススタディで、「メンタルスイッチ」をマスターせよ!
序章 人はなぜ「引きずってしまう」のか?
第1章 切り替えを司る「メンタルスイッチ」のしくみ
第2章 「切り替える」とはどういうことか―メンタルスイッチ5つの誤解
第3章 メンタルスイッチを軽くする実践トレーニング
第4章 切り替え力が試される21のケーススタディ
第5章 それでも「引きずる人」へのヒント
(プラスからマイナスへ)
意識と潜在意識を総合的に動かすメンタルが、その人の可能性を開花させる方向へと動いている時が「プラスシステム」、その逆が「マイナスシステム」。
この2つは、どちらもエネルギーだ。
人はよく、前向きな人を「強い人」、暗くネガティブな人を「弱い人」などと評する。
しかし、これは強弱の問題ではない。
エネルギーがプラスに向かっているかマイナスへ向かっているかの違いだけなのだ。
方向さえ転換できれば、自滅に使っていたエネルギーをそのまま自分を生かす方向へと変えられる。
何も「強くあらねば!」とあがく必要もない。
(切り替えスイッチの考察)
・呼吸は、唯一無二の「意識と潜在意識にまたがる存在」なので、呼吸を通路にして潜在意識に何か伝える。
・スポーツ実況のアナウンサーになったつもりで、緊張した自分を実況してみる。「木村選手、緊張しております。おっと、手にじっとり汗をかいているようだ!・・・」
・風呂に入る自分をイメージする。
嗅覚は石鹸のにおい、触覚はお湯の温かさなど五感は何を感じているだろうか。
誰しも入浴時はリラックスモードとなる。
体の芯から解放され、プラスに共鳴しやすい自分に戻す
質問する力
昨日の午前中は、経営会議。
人事異動、グループ編成など内部組織に関することに時間を費やす。
午後は、お客様の面談など慌ただしく、時が過ぎる。
夕刻から髪を短く刈り、現在、寝台特急「北陸」にて、ブログを更新中。
ガタンゴトンと心地よく揺れるも、もはやこれ以上寝れぬ。
この電車は、金沢駅を22時18分に出発し、6時19分に上野駅へ到着する。
車中、読んでいる本は、大前研一氏の「質問する力」。
「地価の下落は予想できた」という第一章は、胸に響く。
「1991年から1996年ぐらいまでにに家やマンションを購入した方は、毎日が吐息の日々のはずです」から始まる文章を読み始めると、なるほど、貸し方の借金だけがなかなか減らず、借り方の資産だけが価値減少し、どんどん債務超過状態になる様が理解できる。
国家政策の狙いなど、マスコミが報じない本質を見抜く大切さを本書は教えてくれる。