はじめに ~ 更なる共済推進
2019年、TKC北陸三共済推進委員長を拝命してから、三共済を推進しております。
先日、北陸三県の支部例会で、芳野先生とインタビュー形式で動画を配信しました。
その中で、平成23年から事業主以外にも共同経営者が加入できることになったことを紹介しました。
1事業主につき2名まで、専従者の配偶者と子供が加入できます。
また専従者以外でも経営参画していれば第三者従業員でも加入できます。
事業主はほとんど加入ができているという場合、推進余地があります。
現在、当グループでは、共同経営者で加入しているかどうか確認しています。
1.共同経営者としての配偶者
経理を担当している配偶者の資産形成に着目する。
大切な配偶者の老後について、配偶者自身の独自資産の形成に小規模企業共済は有効です。
専従者給与を上げると同時に加入を進める。
2.共同経営者としての子供
子息や令嬢を後継者とする場合、後継者としての自覚を促すことや会社の財務内容を教えることは大事です。
後継者が40代後半となってもなお、現場しか知らない後継者も多く存在します。
小規模企業共済加入の要件として、共同経営者としての経営参画要件を満たす必要があります。
小規模企業共済加入をきっかけに後継者育成を始めることができます。
3.加入上の留意点
小規模共済は早期加入が有利です。
子供が役員ではないから加入できないではなく、子供を役員にして加入させましょう。
ただ、子供の加入推進には、留意が必要です。
先代経営者と折り合いが悪く、転職した場合のリスクがあります。
共同経営者の退任は任意解約扱いで、加入12か月未満では解約手当金は受給できません。
解約手当金を受給できたとしても、加入240か月未満は元本割れです。
また、退職所得ではなく、一時所得となり、課税上不利になります。
辞めないかどうか、加入する場合は事前に協議が必要です。
また、配偶者と離婚した場合にも上記と同じようなことになりますので、ご注意ください。


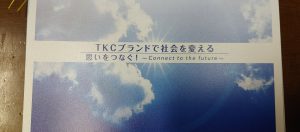
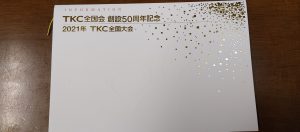 TKC全国会は1971年に創設されてから本年50周年を迎えた。
TKC全国会は1971年に創設されてから本年50周年を迎えた。

 6月29日に表題の定期総会が開催され会場出席した。
6月29日に表題の定期総会が開催され会場出席した。
 3月19日に環境省地球環境局長から表記の協力要請の文書が自宅に届いた。
3月19日に環境省地球環境局長から表記の協力要請の文書が自宅に届いた。
 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が設立から30年が経過した。
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が設立から30年が経過した。
