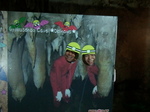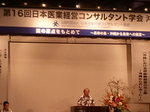NAC21定例会で有森裕子氏の講演を拝聴する。
日時:2012年12月18日(火)18時~19時30分
場所:丸ノ内センチュリーコート
テーマ:「すべてを力に」

「やめたくなったら、こう考える」有森裕子氏(PHP新書)をベースとした人間賛歌。
拝聴後、とても元気になります。
プラスもマイナスもすべてを力に変えていく気概を学ぶ。
僕らには夢がある。
大きい夢を実現するには時間がかかる。
将来を想うと不安だから、人間は、その不安から逃れようとする傾向にある。
「こんなもんだろう」と決めつけると楽だから。
自分を信じて、諦めないでほしい。
信念で不安を払拭してほしい。
また、 「なぜ」ではなく「せっかくこうなんだから」と考える。
時間が限られているので、立ち止まっている場合ではない。
≪お知らせ≫
「サンデージャポン」(青木アナウンサーがTBS卒業で最後の出演)の後、何本かのCMを経て、「株式会社 木村経営ブレーン」を紹介頂く。
関係各位、有難うございます。
御礼申し上げます。
2012年12月23日(日)11時24分~30分
提供:SMBC日興証券金沢支店
企画:MRO
制作:メッセージ
(撮影打ち合わせ)
第一回 11月20日(火) 初面談、内容ヒアリング
第二回 11月29日(木) シナリオ決定
第三回 12月6日(木) 撮影日(挨拶、掃除、朝礼、幹部会議の風景)
第四回 12月19日(水) 最終確認